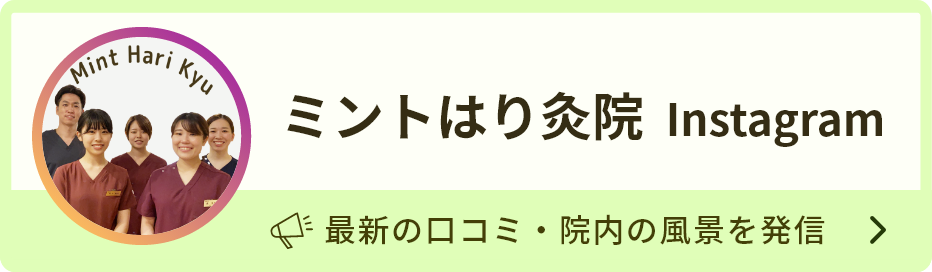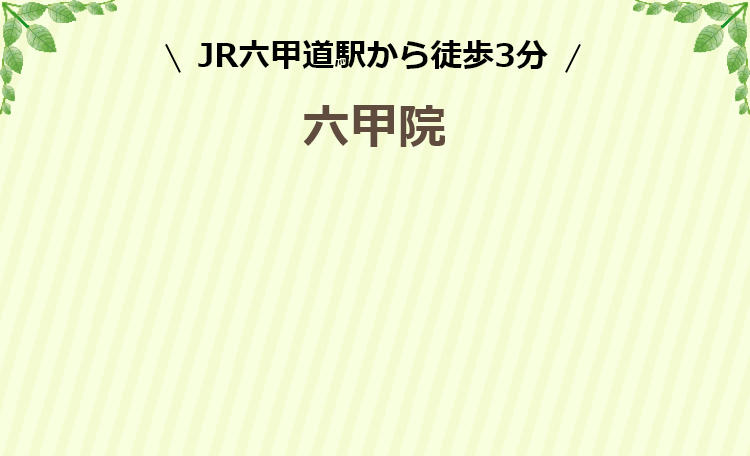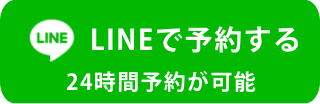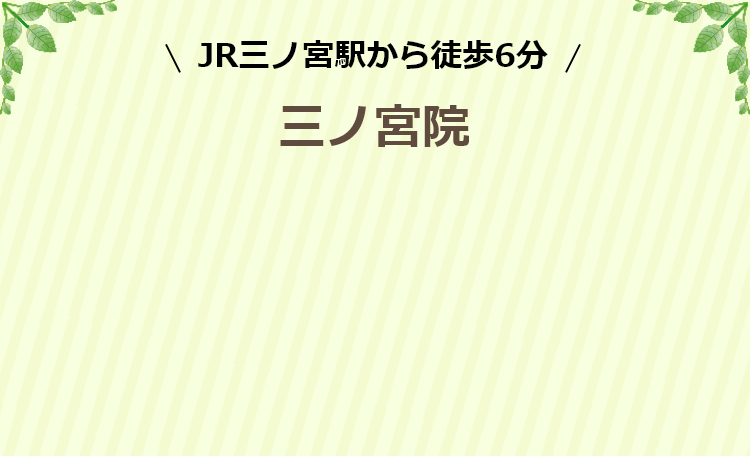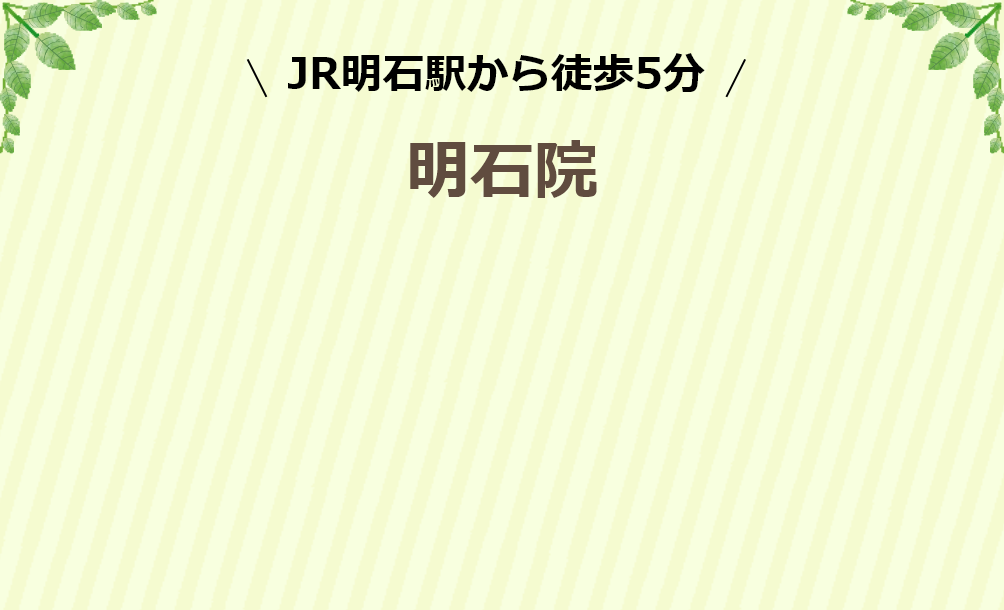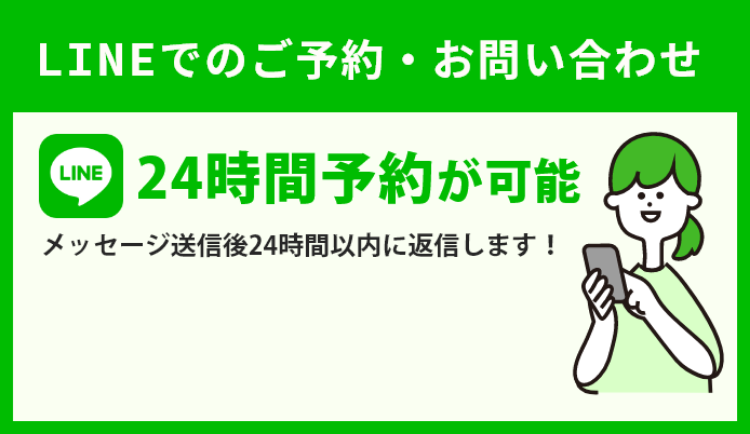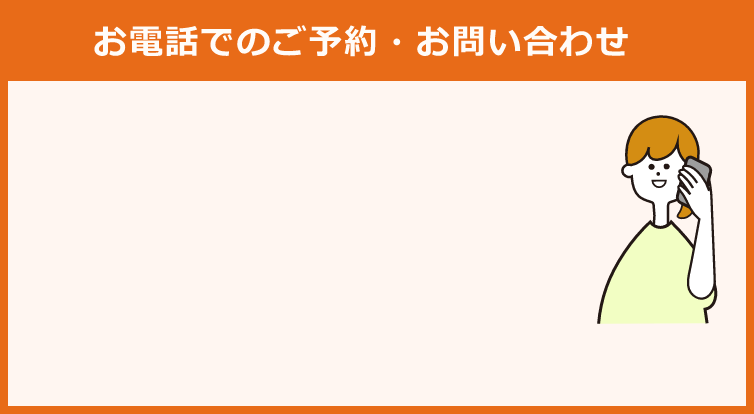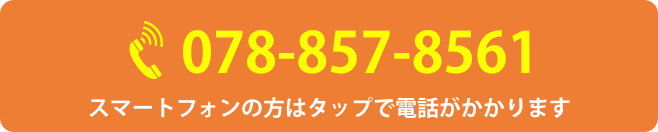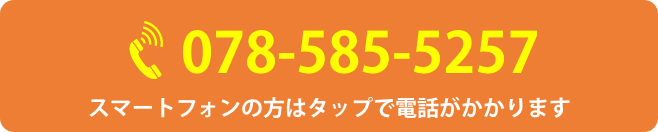投稿日:2025年4月11日
鍼灸ってどんなもの?効果をわかりやすく解説
カテゴリ: Q&A(よくある質問)

鍼灸が良いって効いたけど、実際のところどうなの?
自分の症状に対応しているの?まわりに受けた人も少ないからよくわからない・・・。
やっぱりやめておこう。って思う人は沢山います。
なぜなら鍼灸の受療率は5%で整体院などの1/5以下ほどしかありません。
情報が少なくて何をされるのかがわかりにくいですよね。
今回は鍼灸がどんな症状に対して効果を出すことができるのか?について解説していきます。
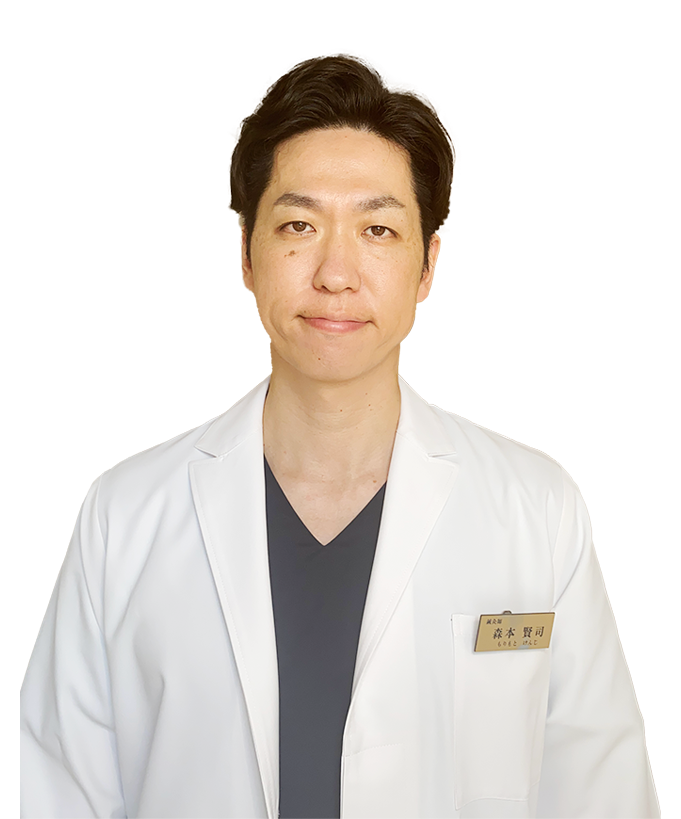
この記事の執筆者
ミントはり灸院 院長
森本 賢司
高度専門鍼灸師
【略歴】
神戸東洋医療学院卒業
神戸東洋医療学院にて河村廣定先生に師事
明治国際医療大学 大学院 修士課程 修了
神戸東洋医療学院 非常勤講師
【資格】
はり師免許証・きゅう師免許証
鍼灸はどんな症状に効くのか
実は鍼灸治療の適応範囲は非常に広いです。
よく思い浮かびそうな、肩こりや腰痛はもちろんですが、自律神経失調症や耳鳴りから過敏性腸症候群からパニック障害、味覚障害や難病なども対応しています。
なぜ?こんなに適応範囲が広いかというと、その人の治す力を使って治療を組み立てているからなんですね。
多くの症状は自分自身の力(免疫力)で治すことができます。
それができない、弱った状態が病気や症状が出ている状態です。
それを手助けするのが鍼灸なので、適応範囲が広くなるわけです。
肩こり・腰痛だけじゃない鍼灸の適応症
実際にWHOが認めた疾患としては以下があります。
① 神経系疾患:神経痛・神経麻痺・痙攣・脳卒中後遺症・自律神経失調症・頭痛・めまい・不眠・神経症・ノイローゼ・ヒステリー
② 運動器系疾患:関節炎・リウマチ・頸肩腕症候群・頸椎捻挫後遺症・五十肩・腱鞘炎・腰痛・外傷の後遺症(骨折、打撲、むちうち、捻挫)
③ 呼吸器系疾患:気管支炎・喘息・風邪および予防
④ 消化器系疾患:胃腸病(胃炎、消化不良、胃下垂、胃酸過多、下痢、便秘)・胆嚢炎・肝機能障害・肝炎・胃十二指腸潰瘍・痔疾
⑤ 代謝内分秘系疾患:バセドウ氏病・糖尿病・痛風・脚気・貧血
⑥ 生殖、泌尿器系疾患:膀胱炎・尿道炎・性機能障害・尿閉・腎炎・前立腺肥大・陰萎
⑦ 婦人科系疾患:更年期障害・乳腺炎・白帯下・生理痛・月経不順・冷え性・血の道・不妊
⑧ 耳鼻咽喉科系疾患:中耳炎・耳鳴・難聴・メニエル氏病・鼻出血・鼻炎・ちくのう・咽喉頭炎・へんとう炎
⑨ 眼科系疾患:眼精疲労・仮性近視・結膜炎・疲れ目・かすみ目・ものもらい
⑩ 小児科系疾患:小児神経症(夜泣き、かんむし、夜驚、消化不良、偏食、食欲不振、不眠)・小児喘息・アレルギー性湿疹・耳下腺炎・夜尿症・虚弱体質の改善
もちろんこれら全てでエビデンスがあるというわけではありませんが、鍼灸で有効性があると言われているわけです。
もちろん、鍼灸師ごと、鍼灸院ごとで方針や技術の違いがあるので、全ての鍼灸院が同じように対応しているとは限りませんので、行こうと思っている鍼灸院のHPなどを確認してください。
症状名が書かれていれば対応していると言えますし、書かれていないくても近しい疾患があれば問い合わせすると「対応できる」という返事があると思います。
病院のように「〇〇科」とかあれば簡単に判別できそうですがそれができないのが法律の縛りもあります。
ただ、最初に説明したように体の中から変えるのを手伝うのが鍼灸なので幅広く対応できます。
しかし、魔法の治療法ではないので、奇跡が起きるというわけではありません。あくまでコツコツと変化を積み重ねていくと考えてください。
精神的ストレス・メンタル不調への効果
「色々と対応しているはわかったけど、いわゆるメンタル疾患はどうなの?」という疑問が出てきます。
確かに心理的なアプローチは我々の専門外です。
実は日本や海外でうつ病の鍼灸治療のアプローチに対する論文が沢山でており、それをまとめた論文によると、一般的な病院の治療と併用することで改善効果が高まることが多数報告されています。
うつ病は心理的なアプローチだけでなく、身体的なアプローチも改善に向けて有効です。不眠や体の痛みなどが愁訴としてあるからです。
体の不調も精神的なストレスになりうるわけです。
そういう意味で鍼灸はメンタル系の疾患にも効果を出すことができます。もちろん同時に専門医の心理的なアプローチを受けることは必須です。
慢性疲労や体のだるさへのアプローチ
「なるほど、病院との併用に効果があるわけか」
「じゃあ、そもそも不調だけど原因不明とかは?」
じつはこういった検査で出ない不調に対するアプローチは鍼灸がもっとも得意としているとも言えます。
病院での検査には数字としてある一定以上を超えないと異常と判定されません。そこが患者さんの間隔と乖離してしまう理由となります。
数字で判定することはとても大切なことなんですが、そればかりで判断してしまっても不調は改善しませんし、悩みは続くわけです。もちろん不必要な医療を提供しないということも大切なことではありますが。
こういった見えない不調を不定愁訴といったり、慢性疲労という表現をします。
最近はこういった悩みの方が増えており、病院としても対応に困っているそうです。
鍼灸は検査の数値よりももっと低いところの不調を見つけることができます。
だからこそ、見えない不調を不調として判断できるので、改善にむけた手立てを提案することもできるわけです。
不調を体で感じるということは、体のサインとしては現れているはずです。それを鍼灸独自の方法で見つけるというわけですね。
鍼灸が効きやすい人の特徴とは?
適応範囲の広い鍼灸ですが、個人差があると聞いたことはないでしょうか?
「私は相性がよかったよ」とか「あなたにおすすめかわからないから自分で探してね」とか。
最初に書いたように鍼灸はその人の身体の治す力を使うわけなので、免疫がない人は存在しませんから、鍼灸に合う合わないは無いはずです。
ただ、効果が出やすい、出にくい人というのは実際に存在します。
それはどんな人か解説します。
体質・生活習慣の傾向
金属アレルギーなどがないことが前提になって、普通に施術が受けられる人で効果に差が出る場合は、体の力がどれだけの期間低下しているかが効果の差が現れます。
長期間低下していると、鍼をしてもすぐには体も反応してくれません。
体が忘れているようなイメージです。
これは筋肉においても同じようなことがあります。
かつて筋トレをしていた人が、しばらく筋トレをしなくなったとしても、再開するとすぐに筋力量が復活するケースがありますl
これは、神経系が維持されているから刺激に対して体がするに反応しやすい状態が維持できているからなんです。
これまでの過ごし方や生活習慣にこういった影響が出やすくなります。
なので、これが個人差となって鍼灸治療の効果の違いが現れるわけです。
ただ、最終的にはちゃんと体は反応するようになっていきます。
登山の道のりが違うというイメージでしょうか。
一度歩いた道は残っていて、未開拓の道は生い茂って進むのが大変ですよね。
運動習慣がある人、食事のバランスが良い人、睡眠の質が良かった人などは鍼灸治療の反応も早くなると考えて下さい。
効きにくいケースもある?
病気や不調になるわけなので、生活習慣が悪化していることがその引き金になっています。それが鍼灸を受けている期間もかわらず悪いままの人がいますが、そうなると良くすることと悪くすることが綱引きをしている状態になるので、いつまでも効果が出ない場合があります。
病院の薬や治療などは、そういったことも関係なく効果を出すことができますが、鍼灸はあくまで体の変化を手伝っているだけなので、悪い生活習慣を無効にするほどの強い反応を起こすことはできません。
運動をしても食事を変えないとダイエットが成功しないのと同じです。
そういった意味で、治療に集中して、生活を改める期間が作れない人は「効きにくい」と感じるかもしれません。
まとめ
今回は鍼灸の効果についての疑問を解説しました。
体がコツコツ変わっていくのって、煩わしいなと思うかもしれません。
ただ、それで得られた体、健康って大事にしようと思いませんか?
薬で痩せる方法もありますが、きっとまた暴飲暴食をしてリバウンドを繰り返すと思います。
それを繰り返すたびに体には見えないダメージが蓄積されていきます。
鍼灸の最大の効果は自分の身体や健康への認識が変わることなのかもしれません。
体質だけじゃなく、意識も変えたいと思うならぜひ鍼灸を試してみてください。
当院「ミントはり灸院」は、根本から改善することに特化した神戸の鍼灸院です《年間10,000人超の実績》。六甲道駅3分”六甲院”/三ノ宮駅6分”三ノ宮院”/明石駅5分”明石院”の3店舗がございます。全室個室でマンツーマンで施術しています、ぜひお越しください。