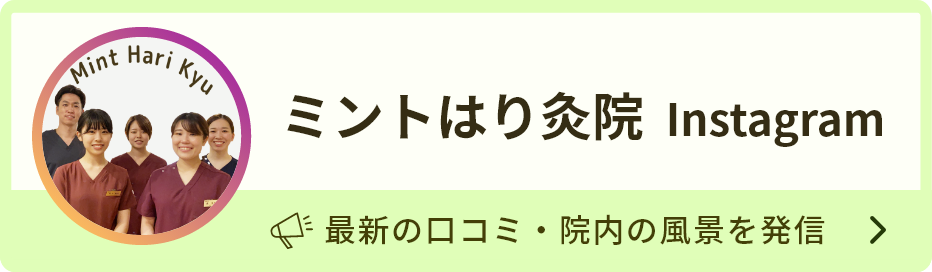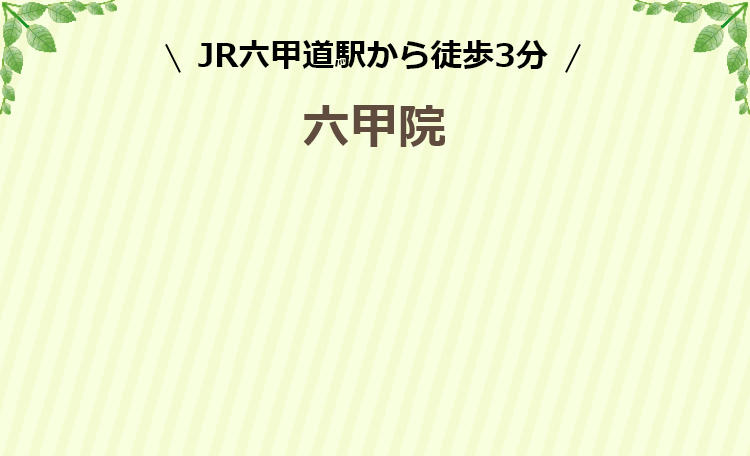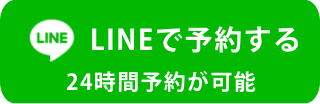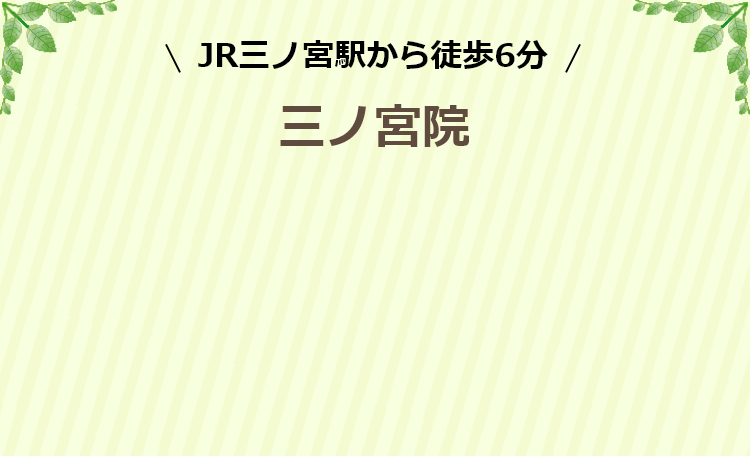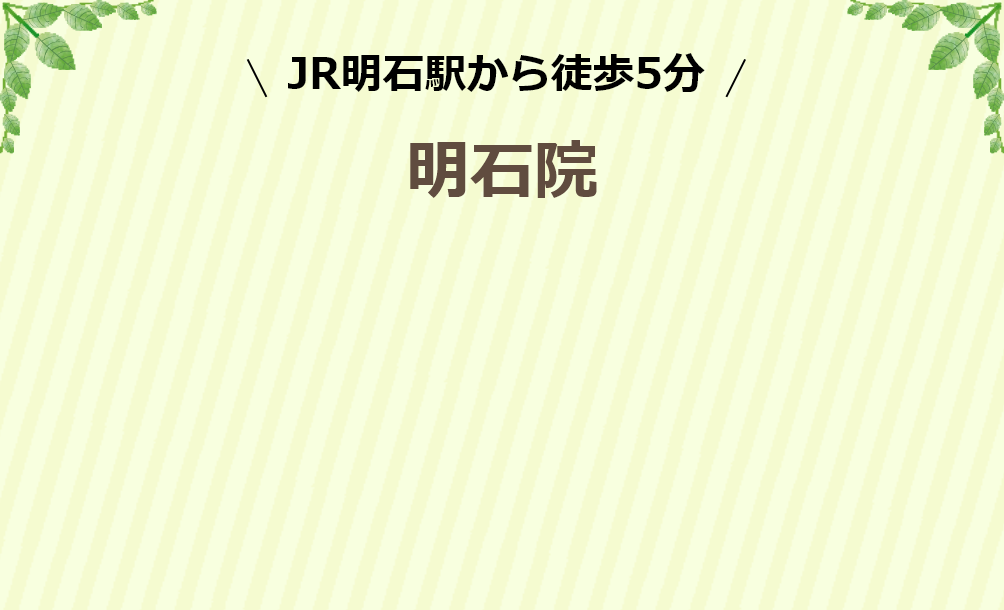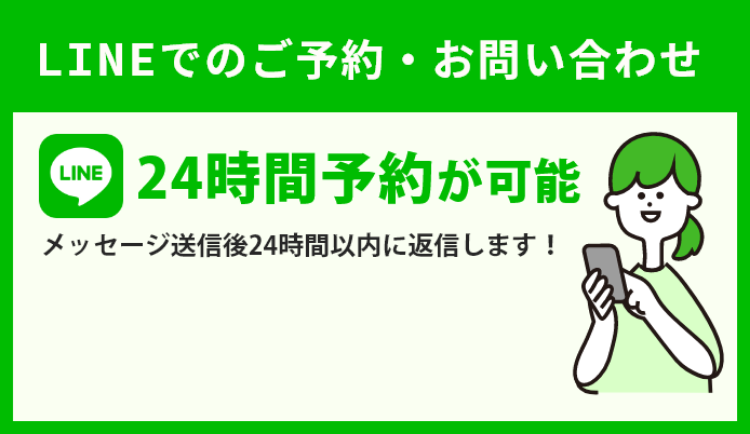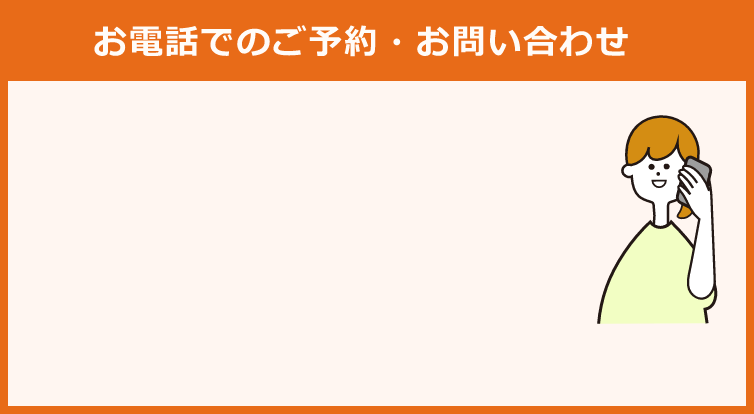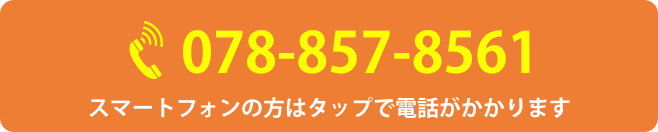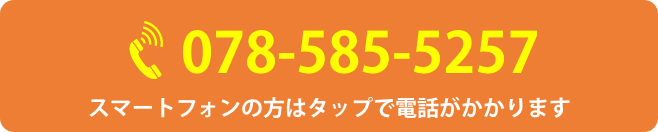投稿日:2020年4月30日 / 更新日:2025年9月18日
逆流性食道炎と動悸はなぜ起こるのか?
カテゴリ: 胃腸障害
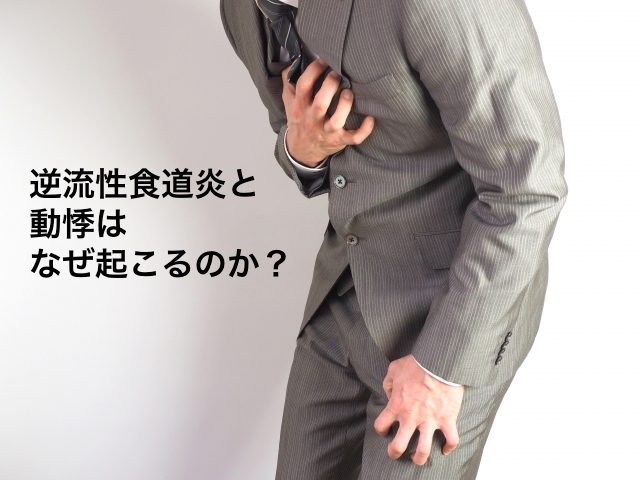
胸がドキドキして息苦しい…「もしかして心臓の病気?」と不安に思ったことはありませんか?
実は、逆流性食道炎でも動悸や息苦しさが起こることがあります。胃酸が食道や喉を刺激し、自律神経のバランスを崩すことで心拍数が上がり、胸の不快感につながるのです。
この記事では、逆流性食道炎と動悸がなぜ起こるのか、そして見極めるポイントやセルフケアの方法まで、わかりやすく解説します。
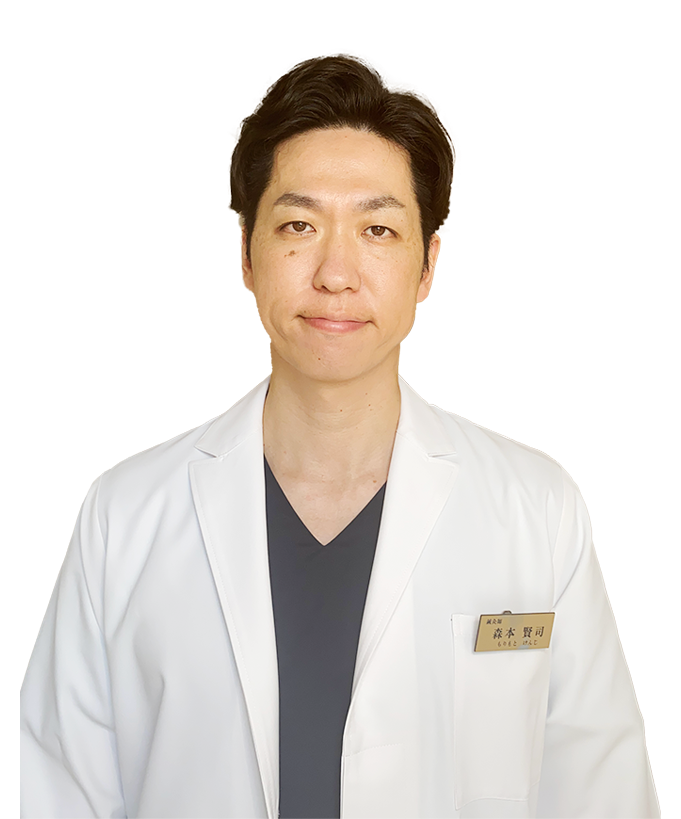
この記事の執筆者
ミントはり灸院 院長
森本 賢司
高度専門鍼灸師
【略歴】
神戸東洋医療学院卒業
神戸東洋医療学院にて河村廣定先生に師事
明治国際医療大学 大学院 修士課程 修了
神戸東洋医療学院 非常勤講師
【資格】
はり師免許証・きゅう師免許証
逆流性食道炎で息苦しい?動悸が起きる?
逆流性食道炎は時に、動悸を引き起こします。
動悸とは心臓の動きが速まったり、鼓動のリズムが乱れる、ドクンドクンと大きく心臓が動いているのが分かる状態です。息苦しさやめまい、震え、発汗を伴うことがあります。
心臓の動きが一時的に悪くなることで、全身に血液が行き渡らず、酸素不足になります。その酸素不足を改善するために心臓がバクバクと激しく動きます。
動悸の原因が直接的に心臓の病気から来ている場合もあれば、パニック障害、貧血、バセドウ病、更年期障害、そして逆流性食道炎が引き起こしていることもあります。
動悸がしたら逆流性食道炎を真っ先に疑う人も少ないので、見落とされがちです。酷いドキドキと強い胸の痛みで救急車を呼び、原因が逆流性食道炎だったケースも聞いたことがあります。
息苦しさが「危険なサイン」かの判断基準
まず何よりも大事なのが「危険」なサインを見逃さないことです。
動悸があったら、胸焼けが原因だ!とすぐには思わずにまずは命に関わる病気でないかをしっかりと確認してから、他の原因を疑うようにしましょう。
思い込んでしまうと病気の発見が遅れてしまいます。
特に動悸は心臓に関わるので慎重に判断しましょう。
もし自分でよくわからない場合はかかりつけ医に相談することをおすすめします。
救急を受診すべき危険なサイン
強い締め付け感や圧迫感が胸の中央や左胸に広がり、左腕や顎、背中に痛みが放散するような場合や、冷や汗、吐き気、強いめまい、失神などを伴う場合には、心筋梗塞などが疑われる危険なサインです。すぐに病院に行きましょう。
また、息苦しさが安静にしていても続く、あるいは急に悪化したり、脈が極端に速くなったり不規則になって強い動悸を伴う場合、さらには吐血や黒色便(タール便)がみられる場合なども、救急対応が必要な病態の可能性があります。
このような症状があるときは自己判断せず、ためらわず救急車を呼ぶか速やかに救急外来を受診しましょう。
逆流性食道炎による息苦しさの特徴
逆流性食道炎による息苦しさは、食後や前かがみの姿勢、就寝時など体位や時間帯によって出やすい傾向があります。
胸やけや呑酸(酸っぱい液がこみ上げる感覚)、喉の違和感などを伴うことも多く、水を飲んだり体を起こしたり、左向きに横になると症状が軽くなる場合もあります。
運動時よりも食事や姿勢によって症状が増悪したり軽快したりすることが特徴であり、こうした場合には逆流性食道炎が原因の可能性があります。
逆流性食道炎で息苦しいのはなぜ?
逆流性食道炎で息苦しさを感じるのは、胃酸が食道や喉を刺激すること、自律神経の働きが乱れること、そして心臓の不調が隠れている場合があることなど、いくつかの要因が重なっているからです。
胸の違和感や動悸がある場合は、それぞれの仕組みを理解することが症状の見極めや対策の第一歩となります。
胃酸による刺激
胃酸が逆流すると食道を刺激します。食道の粘膜への刺激によって、同じ神経領域にある心臓に影響します。食道の痛みによって、心臓の筋肉がきゅっと緊張するのです。
するとドキドキと動悸がしてしまいます。
食道と心臓は全く別のものと考えがちですが、神経領域が同じなので深く関係しています。痛みや炎症は筋肉を緊張させ、さらに痛みや不調を招きます。
別の記事にもありますが、逆流性食道炎によって背中が痛くなることもしばしばあります。
自律神経の興奮による動悸
逆流性食道炎の症状があることで、脳はストレスを感じます。
ストレスに侵された脳から誤った情報が出ることで、心臓の交換神経が興奮します。これが動悸につながります。心臓は自律神経によってコントロールされているからです。
怖いときや運動時にドキドキするのも、寝ているときにリラックスして鼓動が落ち着くのも、自律神経によるものです。
しかし、動悸がすることでさらに不安になり、逆流性食道炎を悪化させることもあります。言い換えれば、これは逆流性食道炎だけではありません。
他の内臓の不調や、ストレスごとが心臓の交感神経を興奮させてしまいます。そこを取り除かなければ、ドキドキや疲れは続いていきます。
心臓の不調による逆流性食道炎→動悸
心臓の不調から動悸になることは理解できますが、心臓の不調が逆流性食道炎を起こし、動悸に繋がっているケースも考えられます。
心臓の不調による不安感というのは、とても強いものです。「心臓は命に関わるもの」という認識があるからでしょう。そして自律神経の乱れによって胃酸が増え、逆流性食道炎が悪化するのです。
そのため、心臓の不調を取り除くことはもちろん、心臓の神経が興奮しやすい状態になることも注意が必要です。お互いが悪さをしてしまうので、どちらも同時に悪さをしないように治療していくことが最適です。
悪さだけでなく、どちらかが良くなった安心感から、症状が改善することもあります。
逆流性食道炎による息苦しさの対処法
逆流性食道炎による息苦しさは、体勢や食後の工夫など、日常のちょっとした対処で和らいだり予防できることがあります。
症状が強いときはまず即効性のある方法で落ち着かせ、長期的には生活環境や習慣を整えることが大切です。
【即効性重視】姿勢・呼吸法による対処
息苦しさが強いときは、まず背筋を伸ばして上体を起こし、胃の圧迫を減らす姿勢をとることが有効です。特に食後は前かがみを避け、ゆったりと胸を広げるように座るだけでも胃酸の逆流が抑えられやすくなります。
食事のとり方も、早食いや大食いは避けたほうが良いです。いきなりメインを食べるよりも野菜の多いものを先に食べることで胃の胃酸過多を防ぐことができます。
また、鼻からゆっくり吸って口をすぼめて吐く「ゆっくり呼吸」を繰り返すことで、自律神経が落ち着き、胸の圧迫感や動悸の軽減につながります。こうした姿勢や呼吸法は薬を使わずにすぐ実践できるため、まず試しやすい方法といえます。
【持続効果】飲み物・環境調整による症状緩和法
症状が起こりやすいときは、水やカフェインの少ないハーブティーなど胃にやさしい飲み物を少量ずつゆっくり飲むことで、喉や食道の刺激を和らげることができます。
会食などで胃に負担がかかると予想されるときは事前に胃薬を飲んでおくことも予防的な効果があります。
また、睡眠時間と睡眠の質の改善はかなり有効です。
胃酸が強い日は就寝前2~3時間は食事を控え、枕やベッドの頭側を少し高くして上体を傾けるなど、逆流しにくい環境を整えましょう。
さらに、室内の温度や湿度を快適に保ち、ストレスを減らす工夫をすることで自律神経のバランスが整いやすくなり、症状の軽減につながります。
逆流性食道炎で息苦しい人の根本改善セルフケア
逆流性食道炎による息苦しさを根本から改善するためには、症状が出たときの対処だけでなく、日常生活の習慣を見直すことが欠かせません。特に「食事」「睡眠環境」「運動・姿勢」の3つを整えることが、長期的な改善への大きなポイントとなります。
胃酸過多と動悸で悩む人向けのセルフケアを紹介します。
食事改善
脂っこい料理や刺激の強い食品、アルコールやカフェインなどは胃酸の分泌を増やし逆流を助長することがあります。食べすぎや早食いも腹圧を高めるため、少量ずつゆっくりよく噛んで食べることが大切です。3回の食事にこだわらず5回に分けるのも胃を休める効果があります。
特に夕食は就寝の2~3時間前までに済ませ、胃が十分に空の状態で横になる習慣をつけることで逆流を防ぎやすくなります。
寝ている最中がもっとも胃を痛めやすいので、夜の食事量を減らすというのも有効です。
稀な例ですが、食べている食品自体が体に合わないというのもあります。それはアレルギーを持っている場合です。病院で検査をしないとわかりませんが、いろいろやってみても食後の胃の重さが改善しない場合はアレルギーを疑いましょう。
睡眠環境の改善
就寝時に胃酸が逆流しやすい人は、枕やベッドの頭側を5~10センチ程度高くして上体をやや起こした姿勢で眠ると、食道への逆流が起こりにくくなります。また、寝る直前の飲食や喫煙、過度な水分摂取を避けることも有効です。快適な温度と湿度を保ち、睡眠の質を高めることも自律神経の安定につながります。
スマホ使用も症状が強い場合は就寝1時間前にはやめておくようにしましょう。
運動・姿勢の改善
腹圧を過剰に高めないようにするためには、日常の姿勢を整え、背中を丸めない・腰をそらしすぎないなどバランスの取れた姿勢を意識することがポイントです。
ウォーキングや軽いストレッチなどの有酸素運動は胃腸の血流改善やストレス軽減に役立ちます。体重の適正化も逆流のリスクを下げるため、少しの運動を日々の生活の中に取り入れてみてください。
心臓の不調を診るには病院の検査だけ?
心臓の病気が考えられるのであれば、もちろん心臓の検査が必要です。しかし心臓の不調、疲れが必ずしも検査で見つかるとは限りません。動悸や息苦しさがあるのに、検査では問題ないことも多々あります。
こういう場合は心臓以外を疑ってみましょう。当院ではさっとと一瞬触れるだけで心臓の不調や、内臓の炎症がわかります。その不調がどこから来ているのかを考え、全身を治療していきます。
内臓と自律神経は非常に深く関わっています。薬で一時的に内臓の症状を取り除いても、また繰り返されることが多いです。もちろん、不整脈などの心臓の不調にも鍼灸で効果を示します。
命にかかわらない心臓の不調に対して病院の対応がいまいちだなと感じたら鍼灸を選んでみるのも一つの方法です。
まとめ
逆流性食道炎による息苦しさや動悸は、胃酸による刺激や自律神経の乱れ、さらには心臓の不調など複数の要因が絡み合って起こることがあります。
胸の圧迫感や強い息切れ、動悸など「危険なサイン」があるときは、迷わず救急受診しましょう。
一方で、逆流性食道炎が原因の可能性が高い場合は、姿勢や呼吸法、飲み物や環境調整などの即効性ある対処に加え、食事や睡眠環境、運動・姿勢の改善など生活習慣の見直しが根本的な改善につながります。
症状の特徴や対処法を正しく理解し、自分に合ったセルフケアを続けることが、息苦しさを和らげる第一歩となるでしょう。
当院「ミントはり灸院」は、根本から改善することに特化した神戸の鍼灸院です《年間10,000人超の実績》。六甲道駅3分”六甲院”/三ノ宮駅6分”三ノ宮院”/明石駅5分”明石院”の3店舗がございます。全室個室でマンツーマンで施術しています、ぜひお越しください。