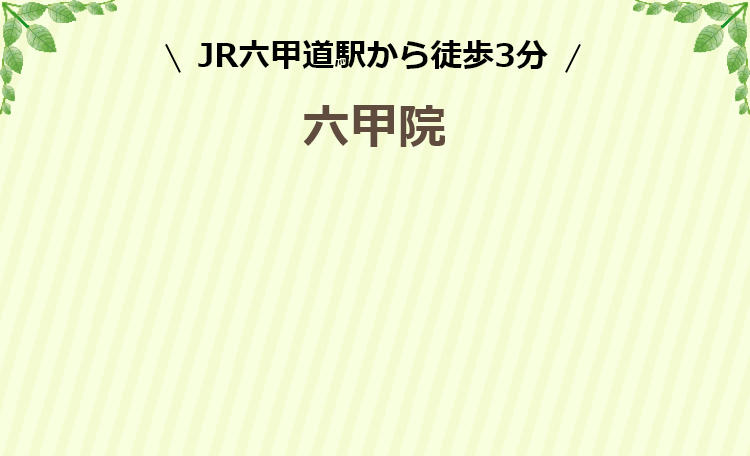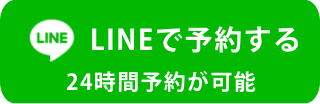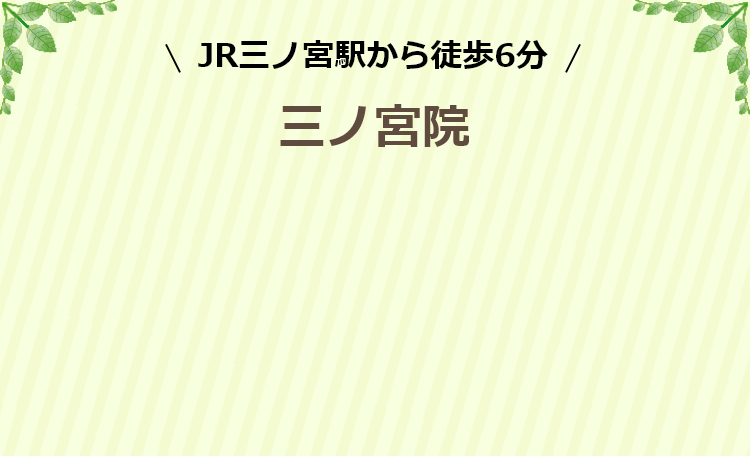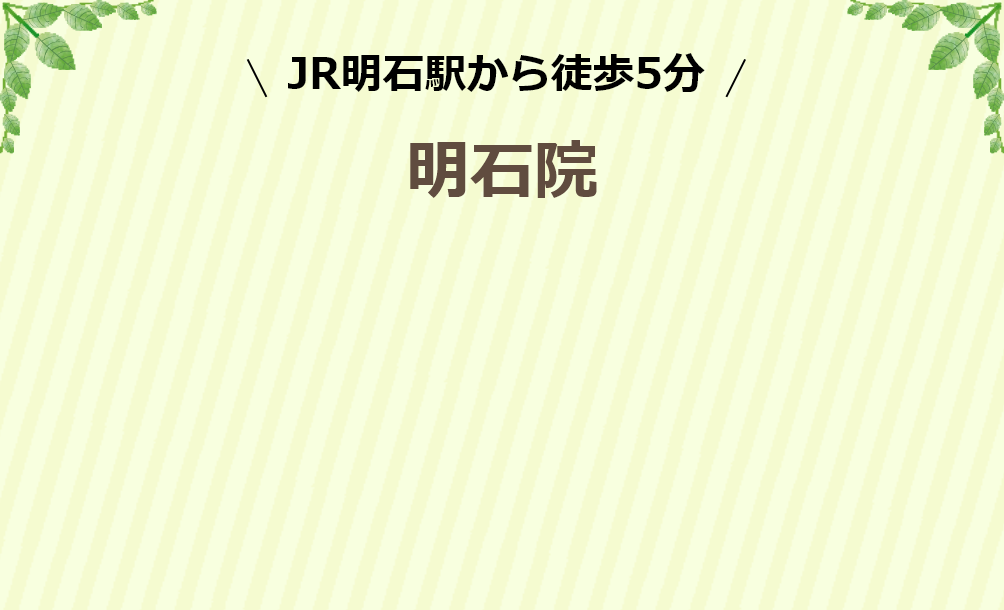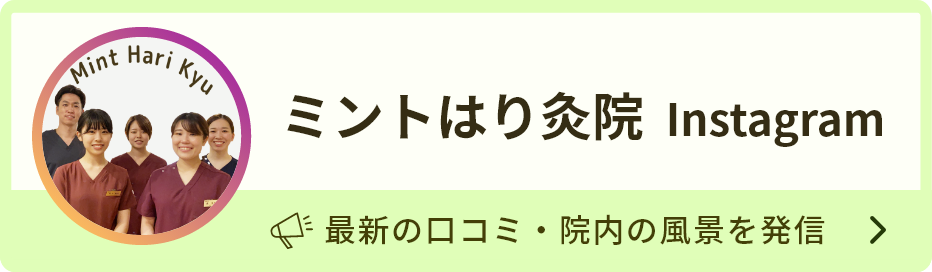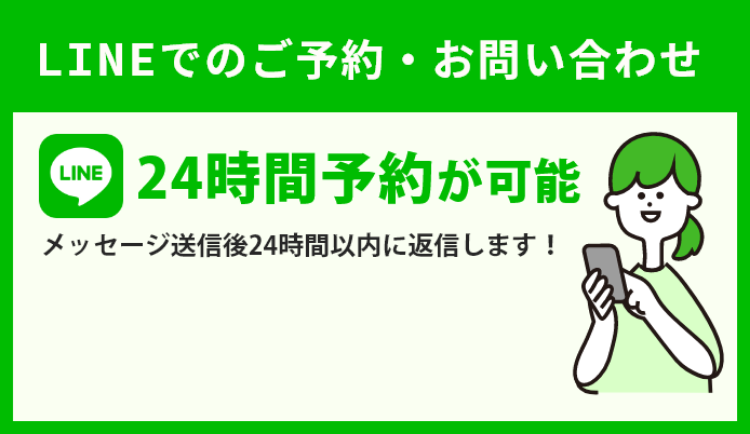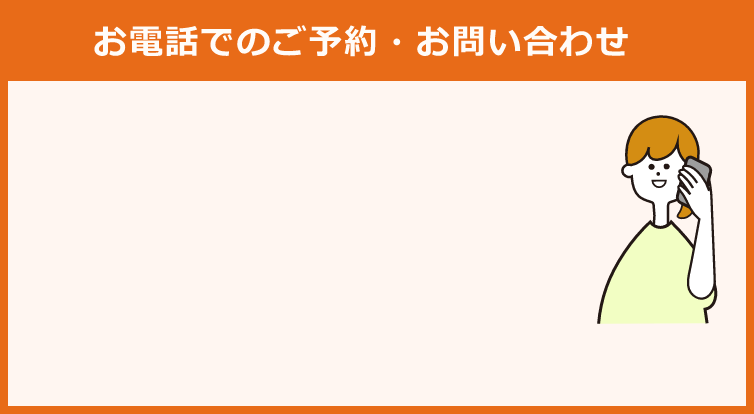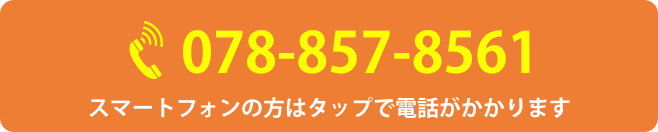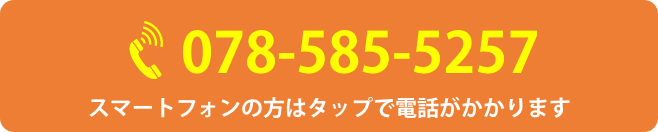投稿日:2020年4月12日 / 更新日:2025年10月23日
顔面神経麻痺はストレスが原因か?
カテゴリ: 顔面神経麻痺

今回は、顔面神経麻痺になってしまった方に向けて、顔面神経麻痺の原因について解説します。 顔面神経麻痺の原因は一般的にストレスと思われていますが、本当の原因は、実は思わぬところにあるのです。
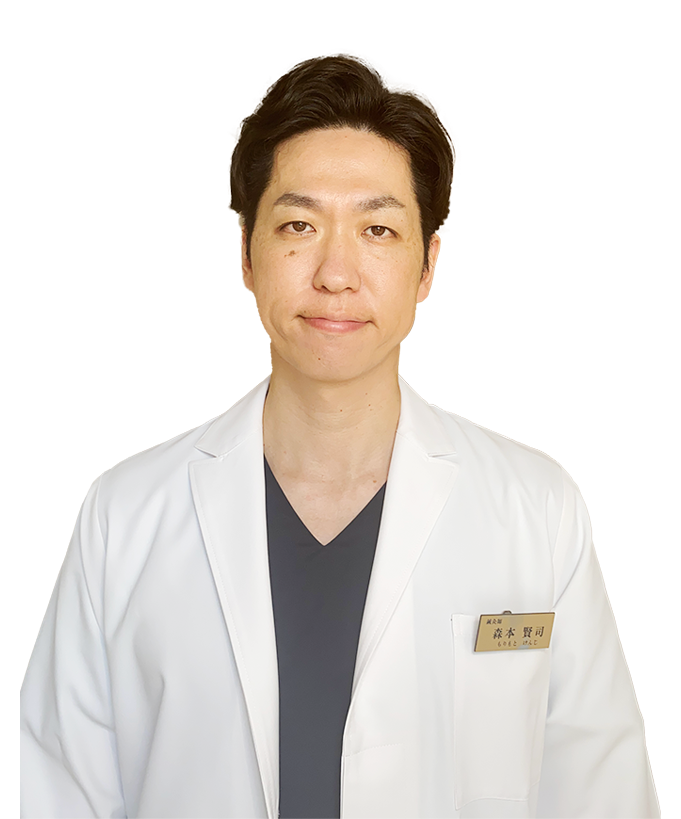
この記事の執筆者
ミントはり灸院 院長
森本 賢司
高度専門鍼灸師
【略歴】
神戸東洋医療学院卒業
神戸東洋医療学院にて河村廣定先生に師事
明治国際医療大学 大学院 修士課程 修了
神戸東洋医療学院 非常勤講師
【資格】
はり師免許証・きゅう師免許証
ストレスによる顔面麻痺?まずはセルフチェック
ストレスのせいかも…と思っている方は、まず次の項目をチェックしてみてください。 一つでも当てはまる場合、顔面麻痺の原因はストレスではなく、体の中で起こっている炎症が関係している可能性があります。
・風邪をひいた後や鼻づまり
・のどの痛みがあった後に症状が出た
・耳の奥やあごの下に違和感や痛みを感じることがある
・味が分かりにくい、食べ物の味が変に感じる
・涙や唾液の量が減った、または増えた気がする
・顔のこわばりやしびれが、数日かけて徐々に強くなってきた
これらは「顔面神経麻痺」に多く見られる特徴です。 ストレスではなく、鼻や耳、のどなどの炎症が神経に影響して起こるケースがほとんどです。 当院で最初に話をお聞きするときには「ストレス」という言葉を使って説明される方が多いのですが、深く質問をしていくと「ストレスはあったが、特別大きかったとは思わない」と気がつくことが多いです。 むしろ忙しさで自分の体調に気がついていなかったことがストレスと原因を混同してしまいます。
顔面神経麻痺の主な症状
【ベル麻痺の主な症状】
・顔の片側が動かしにくい(口角が下がる、まばたきができない)
・笑うと左右のバランスが崩れる
・額にしわを寄せられない
・口から水や食べ物がこぼれる
・味が分かりにくい(舌の前方で味覚障害)
・涙や唾液の分泌量の変化(減るまたは増える)
・耳の奥が痛い、または音が響いて聞こえる(聴覚過敏)
・顔のしびれや違和感があるが、痛みは少ない
【ラムゼイ・ハント症候群の主な症状】
・ベル麻痺と同様の顔面麻痺(片側のみ)
・耳やその周囲に強い痛みが出る
・耳の中や口の中(舌・口蓋)に水ぶくれ(帯状疱疹の発疹)ができる
・めまいやふらつき(平衡感覚の障害)
・耳鳴りや難聴が伴うことがある
・味覚の低下、涙や唾液の異常分泌
・発熱や倦怠感など全身のだるさ
ベル麻痺は主に「ウイルス感染による炎症」が顔面神経を圧迫して起こるのに対し、 ハント症候群は「水痘・帯状疱疹ウイルス」が再活性化して発症します。 いずれもストレスそのものが原因ではなく、体内の免疫力が低下したタイミングで炎症が起こることが多いです。
顔面神経麻痺はストレスが原因ではありません
顔面神経麻痺の原因は、強いストレスだと思っている方も多いのではないでしょうか?確かに、顔面神経麻痺は、精神的ストレス・過労が引き金となって起こることがあります。
ただし、精神的ストレスや過労そのものが、顔面神経麻痺を引き起こすわけではありません。これらはあくまで間接的な原因に過ぎず、顔面神経の炎症を起こす直接的な原因は、もっと別のところにあります。
誰でも程度の差こそあれ、ストレスを感じながら生きています。悪いことが起こったときだけでなく、嬉しいことが起こったときでも、人によっては大きなストレスを感じることがあります。 社会的なストレスは誰にでもあるもので、決して特別なものではありません。ですから、どんなに負荷がかかっていても、しっかり睡眠さえ取れていれば基本的に問題なく、体に不調をきたすことはありません。
本当の原因は鼻や耳、咽の炎症
では、顔面神経麻痺を引き起こす直接の原因は何だと思いますか?
実は、顔面神経麻痺の本当の原因は鼻や耳、咽の炎症です。咽や鼻、耳に何らかの炎症が起こっていて、それが顔面神経にまで広がって起こるのが顔面神経麻痺なのです。 鼻・耳・咽に起こる炎症としては、鼻炎や副鼻腔炎、外耳道炎や中耳炎、扁桃炎や咽頭炎などがあります。これらは風邪をひいたときに多く起こるものです。
こうした鼻・耳・咽の炎症は、炎症の拡大というかたちで、顔面の神経にも直接悪い影響を及ぼします。また、慢性炎症でも、局所の循環低下や免疫の低下を起こすため、それが顔面神経の感染になることもあります。 このように、顔に近い部分にまず局所的な炎症が起こって、それが治らないうちに、より大きな神経である顔面神経にも炎症が広がっていったものが顔面神経麻痺なのです。
炎症が広がるということは免疫力が低下
鼻・耳・咽の炎症から顔面神経へと炎症が広がるのは、体の全体の免疫力が低下しているサイン。
日頃の疲れが蓄積していて、体に悪影響を及ぼしていると考えられます。これをストレスと考えるなら、ストレスによって顔面神経麻痺が起こるということもできるでしょう。 まず、ストレスで免疫力が下がり、風邪を引くなどして鼻・耳・咽に炎症が起こります。
ここで体力が回復すれば何ら問題ありません。しかし、そのまま体力が回復せず免疫力が低下しづけると、炎症範囲がどんどん広がって、顔面神経麻痺につながる危険性が出てきます。 顔面神経麻痺になってしまうと、日常生活に大きな支障をきたすことも。ですから、こうなる前に、体調がよくないことに自分で気がつかなければなりません。
たとえば、免疫力が低下すると腹部に不調が出やすくなります。いつも通り過ごしているのに、最近何だかお腹の調子が悪いなというときは、疲労がたまっている可能性があります。そんなときは、疲れているのだなと自覚して、十分な睡眠を取って休養につとめ、体力と免疫力を回復するよう心がけましょう。そうすれば、顔面神経麻痺になるリスクを減らすことができるかもしれません。
顔面神経麻痺は治るのか?
顔面神経麻痺は、適切な治療を受ければ多くの場合で回復が期待できます。 決め手になるのは重症度と治療開始時期です。 ここでは、病院で行われる主な治療法と、それぞれの治癒率について説明します。
【ステロイド治療】 発症からできるだけ早く(できれば72時間以内)に行われるのが「ステロイド投与」です。
これは神経の炎症やむくみを抑えるための標準的な治療法です。
・目的:神経の炎症・浮腫を抑え、神経線維の回復を促す
・方法:プレドニゾロンなどを5~10日間ほど内服、重症の場合は入院点滴。
・治癒率:およそ70~85% ただし、糖尿病や高血圧のある方では慎重な管理が必要になります。
【抗ウイルス薬】 ウイルス(特に単純ヘルペスや帯状疱疹ウイルス)が関与していると考えられる場合、 ステロイドと併用して抗ウイルス薬(アシクロビルやバラシクロビル)が投与されます。
・目的:神経内でのウイルス増殖を抑える
・方法:1週間程度の内服または点滴 ・治癒率:ステロイド単独と比べて大きな差はないが、重症例では併用が有効とされる
【リハビリ】 急性期を過ぎて回復期に入ると、顔面筋の拘縮や“連合運動(変な動きの連動)”を防ぐため、表情筋のリハビリが行われます。
・目的:筋肉の動きを取り戻し、左右差を改善する
・方法:表情筋マッサージ、電気刺激、温熱療法など
・治癒率:リハビリを継続した場合、軽~中等度の顔面神経麻痺では80~90%が改善 【手術療法】 非常に重症で、神経が完全に断裂・圧迫されている場合に限り、神経減圧術などの手術が検討されます。
・目的:顔面神経を圧迫している骨や組織を除去
・方法:耳の後ろからのアプローチで顕微鏡下に行う
・治癒率:適応例は限られるが、術後に部分回復するケースが約60~70% 神経の回復というよりは神経がこれ以上損傷しないことを目的としています。
【全体の予後】
・ベル麻痺:発症後早期に治療を始めれば、約80~90%がほぼ完治
・ハント症候群:回復率はやや低く、50~70%前後にとどまることが多い つまり、顔面神経麻痺は「早期の正しい対応」で治る可能性が高い疾患です。
ただし、ストレスや体質ではなく「ウイルス感染」「炎症」「免疫力の低下」といった 身体の状態が背景にあるため、再発防止のためには体調管理が重要になります。
鍼灸での顔面神経麻痺の治療法
当院では、顔面神経麻痺に対して以下のようなアプローチを行っています。
鼻・咽・耳などの炎症を原因と捉え、顔・首・顎関節周りの筋肉の緊張、循環不良を改善する鍼灸施術を行います。例えば、「顎関節や首の筋肉に疲れが出ていないかを確認」してから、表情筋と関連の深い反応点(ツボ)に鍼を刺して刺激していきます。
温灸やローラー鍼によって、内臓の機能改善・血流改善・自律神経の調整を図り、神経→筋肉→表情筋の連動を取り戻すことを目指しています。 病院との治療と並行して受けることを推奨していますが、多くの場合は投薬治療後または手術後に来る方が多いです。
投薬で取り切れなかった炎症やリハビリだけでは動かしきれない筋肉、損傷した神経の回復を促すことができるのが当院の施術です。
当院での実際の症例・回復例
いくつか当院での患者様の声・経過をご紹介します。
40代男性(神戸市):「X年10月に右側顔面麻痺、目と鼻を閉じられず、耳鼻科でステロイド治療・手術も受けられたが改善が乏しく来院。鍼灸では鼻炎・咽炎・肝臓の影響を含めた全身の状態も調整。初回で“顔が軽くなった”感覚、3回目で「頬の筋肉が動くようになった」、7回目では「目が閉じられるようになり、人目を気にしないほどまで回復」。
50代女性(神戸市垂水区):「発症20日経過後に来院。左側顔面麻痺、瞼開閉困難・口角低下・眉毛下がり・額にしわが寄らない症状。通院を重ね、表情筋・首・咽・鼻部のケアによって改善が見られ左右差がなくなっています。」
他にも沢山の事例があります。病院での治療だけでは回復が難しかったケースでも、鍼灸を併用することで動きの回復・表情の改善やこわばりの改善などがみられました。
回復のための日常生活の送り方
顔面神経麻痺の回復には、日常生活の過ごし方が大きく関わります。体の回復力を高めるためには、無理をせず、バランスを整える生活を意識することが大切です。
「食事」
炎症を鎮め、神経の修復を助けるには、ビタミンB群(特にB12)・たんぱく質・抗酸化成分(ビタミンC、Eなど)を意識的にとりましょう。 揚げ物や糖質の多い食品は炎症を悪化させることがあるため控えめに。味覚が変化している時期は、酸味や香りのある食材(ゆず、しそ、レモンなど)を取り入れると食が進みやすくなります。
「睡眠」
神経の再生は睡眠中に進むといわれています。毎日同じ時間に寝起きし、睡眠の質を整えることが大切です。夜更かしやスマートフォンの長時間使用は自律神経を乱しやすく、回復を遅らせる原因になります。
「運動」
軽いストレッチや散歩など、血流を促す運動がおすすめです。体を動かすことで代謝が上がり、神経や筋肉への栄養が行き届きやすくなります。歩くだけでも顔の筋肉は振動により刺激が入ります。それだけでもマッサージ効果があります。
よくある質問
「発症後はどうすごすのがおすすめですか?」
発症直後は焦らず、体を休めることが最優先です。風邪や疲労で免疫が落ちている状態が続くと、炎症が長引き回復が遅れます。十分な睡眠と栄養を取り、体力を回復させることが大切です。
「鍼灸が良いのはわかるけど、施術に対する不安がある」「顔に鍼を刺すのが怖い」「痛みはあるのか」
当院の施術は非常に細い鍼を使用し、刺激はごく軽度です。施術の目的は「神経に直接刺激を与える」ことではなく、「血流と炎症の改善、自律神経の安定」を促すことです。多くの方が1回目の施術後に「顔が軽くなった」「温かくなった」と体感されています。
治る期間はどのくらい?
発症からおおよそ1年以内は、神経が自然に回復しやすい時期です。 その期間に適切なケアを行うことで、回復スピードが大きく変わります。 また、一度回復しても「違和感」や「ひきつり」が残る方もいますが、鍼灸ではそのような後遺症に対しても有効です。
マッサージはいつから始めて良い?
病的共同運動(まばたきと口角の動きが連動してしまうなど)のメカニズムはまだ明確ではありませんが、皮膚や筋肉への軽い刺激は早期から行うことが推奨されます。 ただし、強く押したり、筋肉を無理に動かそうとするマッサージは逆効果になる場合もあるため、やさしく触れる程度に行うことが大切です。
仕事は休むべき?在宅勤務は可能?
表情が気になって人と会うことがストレスになる場合は、思い切って休むことも選択肢に入れてください。 一方で、実は「顔面神経麻痺の経験者」は意外と多く、そうした人たちから励ましを受けることで気持ちが軽くなる方もいます。 体調が落ち着いてきたら、無理のない範囲で外出や軽い仕事を再開しても問題ありません。
まとめ
顔面神経麻痺は、早期の正しい治療と生活習慣の見直しで回復が十分に期待できる疾患です。
ストレスではなく、身体の中で起きている炎症や免疫の低下が根本原因であることを理解しましょう。正しい原因への理解が回復を早めます。 焦らず丁寧にケアを続けることが回復への近道となります。 不安を感じたときは、一人で抱え込まず、専門家に相談してみてください。
当院「ミントはり灸院」は、根本から改善することに特化した神戸の鍼灸院です《年間10,000人超の実績》。六甲道駅3分”六甲院”/三ノ宮駅6分”三ノ宮院”/明石駅5分”明石院”の3店舗がございます。全室個室でマンツーマンで施術しています、ぜひお越しください。