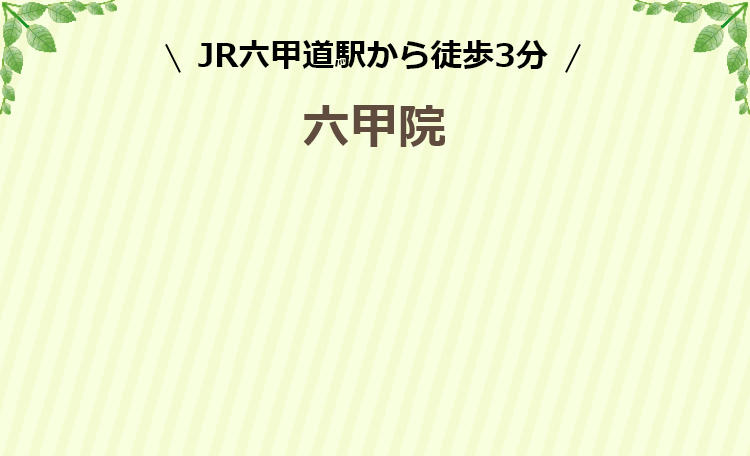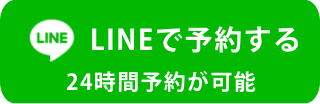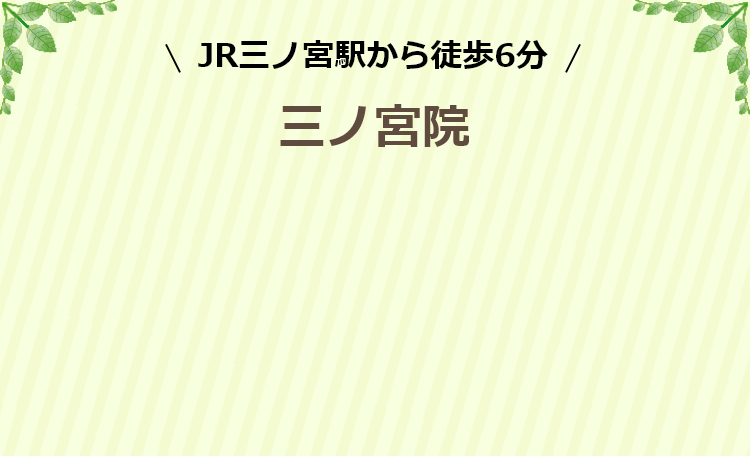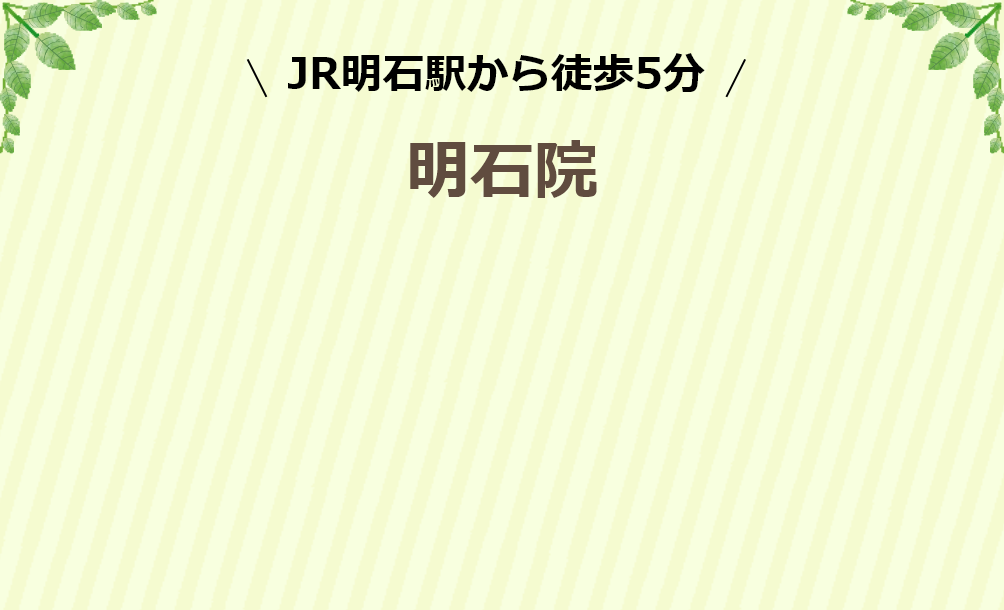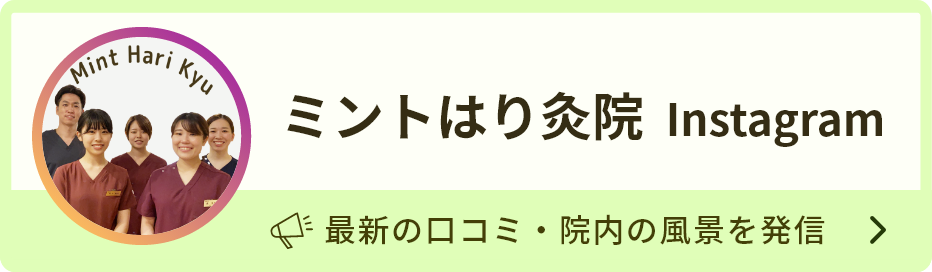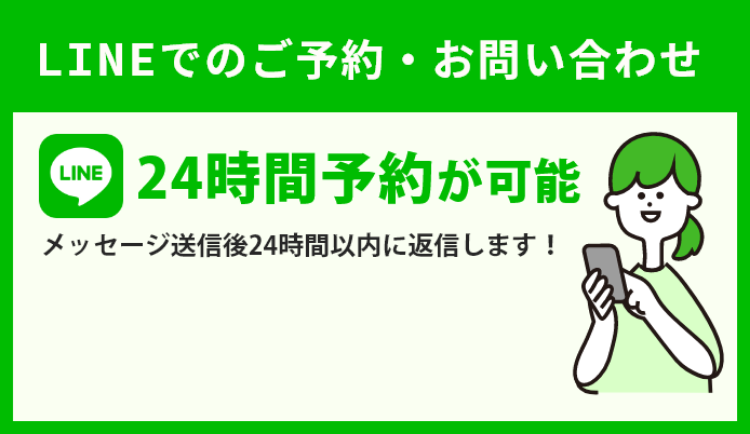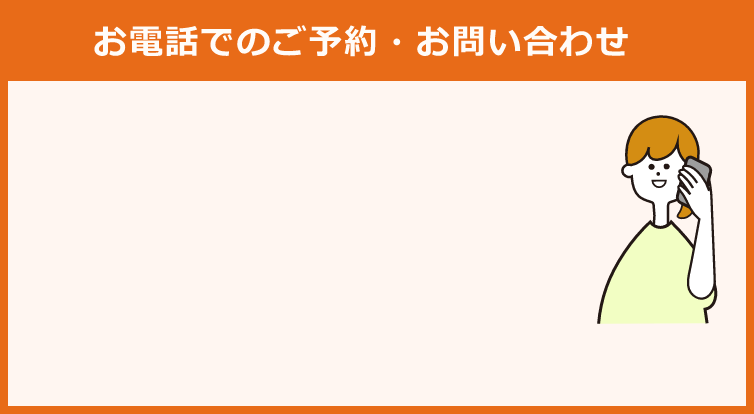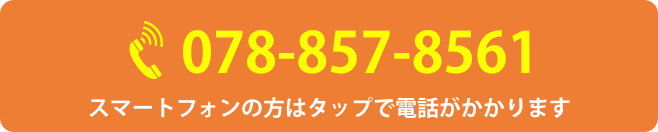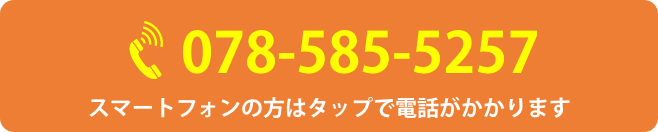投稿日:2020年4月20日 / 更新日:2025年10月9日
食いしばりに鍼は効果的?原因から対処法まで解説
カテゴリ: 顎関節症

食いしばりは鍼で解決できるかもしれません
朝、起きたときに「また顎が痛い…」と感じたことはありませんか?
歯科でマウスピースを作ったけれど、違和感が強くて合わないと思って続かなかった――そんな経験をされた方は少なくありません。
また食いしばりを直さないといけないと言われたけど、なかなか自力ではどうすることもできない。。
実は、そうした「マウスピースが合わない」「食いしばりが治らない」といったお悩みには、鍼治療が有効なケースがあります。
筋肉の緊張やくいしばりを発症する自律神経のバランスに直接アプローチできるため、原因そのものを緩めていくことが期待できるのです。
この記事では、「なぜ鍼が食いしばりに効くのか」そして「自宅でのセルフケア方法」まで、施術歴10年以上の専門家の視点でわかりやすく解説します。
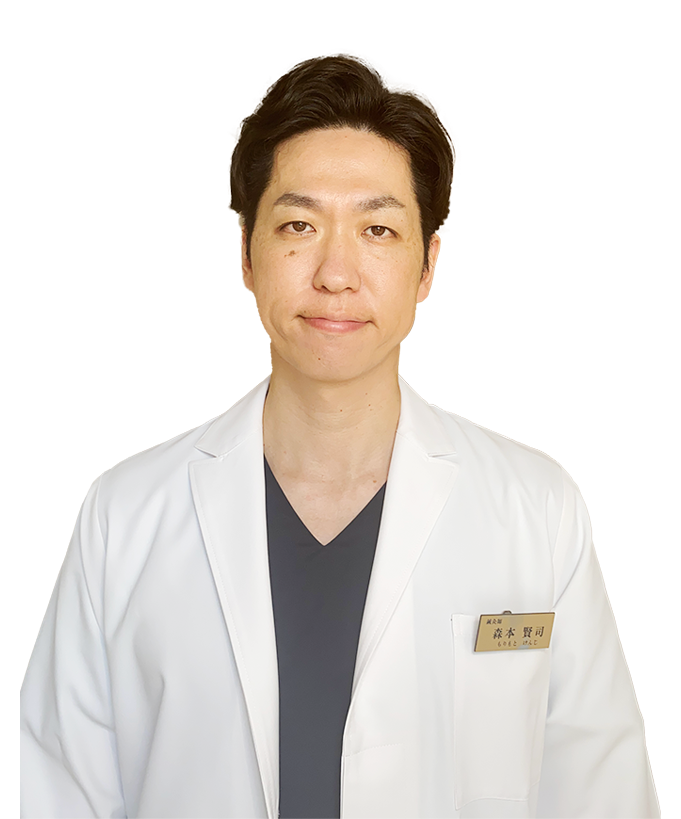
この記事の執筆者
ミントはり灸院 院長
森本 賢司
高度専門鍼灸師
【略歴】
神戸東洋医療学院卒業
神戸東洋医療学院にて河村廣定先生に師事
明治国際医療大学 大学院 修士課程 修了
神戸東洋医療学院 非常勤講師
【資格】
はり師免許証・きゅう師免許証
食いしばりについて
「歯を食いしばる」という言葉には、辞書的には「苦しみや悔しさをじっとこらえる」という意味があります。
ただし医学的にいう「食いしばり」は、精神的な表現ではなく、上下の歯を強く噛み締めてしまう動作そのものを指します。
この状態は、別名「クレンチング症候群」や「TCH(Tooth Contacting Habit:歯列接触癖)」とも呼ばれ、顎関節症や筋肉のこわばり、頭痛などの原因になることがあります。
通常、リラックスした状態では上下の歯の間に2?3ミリほどのすき間があり、歯どうしは触れていません。
しかし、食いしばりのある人は無意識のうちにそのすき間をなくし、1~2時間以上にわたって強い力で噛み締め続けてしまう**ことがあります。
この習慣が続くと、歯や顎、首・肩の筋肉まで疲労が蓄積し、さまざまな不調につながっていきます。
また、食いしばりにはいくつかのタイプがあり、次のように分類されます。
グライディング(grinding):歯と歯を横にこすり合わせる動作。歯のすり減りや知覚過敏の原因になります。
クレンチング(clenching):上下の歯を垂直方向に強く噛み締めるタイプ。顎の痛みや筋肉のこりを引き起こします。
タッピング(tapping):上下の歯をカチカチと繰り返し合わせる動き。神経系の緊張が関係していることもあります。
このように「食いしばり」といっても、その内容や負担のかかる部位には違いがあります。
自分では気づきにくいことも多いため、症状や生活習慣を観察することが改善の第一歩になります。
食いしばりの原因とは
食いしばりの原因はひとつではなく、身体的・心理的・生活習慣的な要因が複雑に関係し合って起こると考えられています。歯科・医療・心理学などの分野でさまざまな見解がありますが、ここでは主な要因を整理してご紹介します。
1. 精神的ストレス・緊張
最も一般的な原因として挙げられるのが「ストレス反応」です。
人は不安・怒り・焦り・緊張といった心理的負担を感じると、体が無意識に力みやすくなります。特に顎周りの筋肉(咬筋や側頭筋)は感情と連動しやすく、我慢や不安を抱えたときに自然と噛み締める傾向があります。
食いしばることで発生する痛みが脳からエンドルフィンを出すことでストレスを解消しているとも言われています。
2. 筋肉の緊張と姿勢の悪化
長時間のデスクワークやスマホ操作などで猫背やうつむき姿勢が続くと、頭の重心が前に傾き、下顎を支える筋肉に常に負担がかかります。
これにより咀嚼筋(そしゃくきん)や首・肩の筋肉が硬くなり、「力を抜こうとしても抜けない」状態が生まれ、食いしばりを慢性化させます。
ちょうど顔を下向きにしたときに奥歯が狭くなって当たるようになります。その時に食いしばりをしていると言われています。
3. 噛み合わせや歯列の不調和
歯科的な観点では、噛み合わせがズレていると一部の歯に過剰な力がかかり、自然な咀嚼運動ができなくなります。
また、親知らずや歯列矯正、詰め物・被せ物の高さの不具合などがきっかけで、顎関節や咬筋のバランスが崩れる場合もあります。
4. 睡眠の質・自律神経の乱れ
睡眠中に起こる食いしばりは、深い睡眠(ノンレム睡眠)への移行がうまくいかないことと関係しています。
夜中に浅い眠りや夢を見る時間が増えると、交感神経が優位になり、体が「緊張モード」から抜けられずに噛み締めを続けてしまいます。
不規則な生活、夜更かし、就寝前のスマホ操作、アルコールやカフェインの摂取も影響します。
5. 運動・筋トレ・スポーツ時の力み
筋トレやスポーツの際に「歯を食いしばる」ことは自然な反応ですが、習慣化すると日常生活にも持ち越されます。
特に重い負荷を扱うトレーニングやゴルフ・テニスなどで強く噛む癖がある人は、顎周囲の筋肉が過剰に発達しやすくなります。
7. 内科的・神経的要因
薬の副作用(抗うつ薬や睡眠薬など)で食いしばりが出るケースや、パーキンソン病などの神経系疾患に伴う筋緊張として現れることもあります。
また、ホルモンバランスの乱れや更年期、自律神経失調などが背景にある場合もあります。
食いしばりが起きやすい状況
一番多いのは夜寝ているときです。その他にはパソコンでの作業中、集中しているとき、ストレスがかかっているとき、テレビを見ているとき、ゲームをしているときなどです。
いずれにせよ、共通しているのが自分の顎を意識していない状況で食いしばりは発生しているわけです。
原因も様々あるように、くいしばりを発症する場面も人それぞれです。ただ、多くの方が同じ状況のときにくいしばりを無意識に習慣的に行っています。
無意識なので状況を認識していない人が多くなります。まずはどこでくいしばりをしているのかを知ることが解決に向けた1歩目になります。
食いしばり症状チェックリスト
1:舌に歯の跡がついている
2:朝起きたときにのどが渇いている
3:口の中にこぶができている
この3つの全てに当てはまった場合は食いしばりをしている危険性がかなり高いです。また、朝から顎が疲れている方も要注意です。
他にも
4:左右の顎の膨らみが違う
5:虫歯じゃないけど歯が痛い時がある
6:顎を開けづらいと感じる時がある
などです。
自分ではよく分からない人は一度歯医者さんでチェックしてもらうと良いでしょう。歯のすり減りや額関節に異常がないかなどがすぐに分かります。
食いしばりに鍼が効く3つの理由
これまで上げた原因に対して明確なアプローチができるのが鍼灸です。
とくに顎関節症は複数の原因が影響し合っていたりするので、一つが改善したからと言って症状が改善するとは限りません。
大事なのは複数の原因に対して並行して改善をしていくことが最短ルートを歩むことになります。
紹介した原因に対してなぜ効果を出すことができるのか、主に3つの理由を紹介します。
理由①:筋肉へのアプローチ
食いしばりの直接的な原因の多くは、咬筋(こうきん)・側頭筋・胸鎖乳突筋など、顎や首まわりの筋肉が過度に緊張していることにあります。
鍼治療では、これらの過緊張した筋肉に直接刺激を与えることで、血流を改善し、筋肉のこわばりを解きほぐすことができます。
筋肉が柔らかくなると、顎の動きがスムーズになり、「噛み締めないと落ち着かない」という状態が自然に減っていきます。
また、鍼によってトリガーポイント(筋肉のしこり)を緩めることで、顎だけでなく肩こりや頭痛などの関連症状も軽減するケースが多く見られます。
理由②:自律神経へのアプローチ
食いしばりは「緊張」や「興奮」が続くときに起こりやすく、これは交感神経が優位な状態です。
鍼治療は、筋肉だけでなく自律神経にも働きかけることができ、交感神経と副交感神経のバランスを整える効果が知られています。
特に睡眠中の食いしばりや、朝起きたときの顎のだるさがある方は、自律神経の乱れが背景にあることが多く、
鍼治療によって「リラックスモード(副交感神経優位)」へと導くことで、夜間の無意識な食いしばりを軽減できます。
理由③:メンタル・感情面へのアプローチ
ストレスや我慢、怒り、不安といった感情を抱えると、体は自然と力が入ります。
鍼治療には、身体の緊張を和らげると同時に、心の緊張をほどく効果もあります。
体が緩むと、脳が「安心していい」という信号を受け取り、気持ちも落ち着いていきます。
これは単なるリラックス効果ではなく、「我慢して噛み締めるクセ」を身体のレベルでリセットしていく作用とも言えます。
そのため、精神的なプレッシャーや完璧主義からくる食いしばりにも、鍼は有効なサポートとなります。
どのくらいで効果を実感できる?即効性と持続性
食いしばりは顎の痛みや顔の変形の改善から、自律神経まで範囲が広くなります。
それぞれの効果の出方に違いがあるので、それぞれについて解説します。
痛みは不快感が強いので、できるだけ早く改善することがQOLを高めるうえでも重要なことです。またそれだけで終わってしまってはすぐに再発してしまうのも特徴なので、再発しない体作りをすることで食いしばりから卒業して悩むことのない当たり前の日常を目標にしましょう。
施術直後~数日で実感できる変化
鍼による筋肉へのアプローチは、比較的早く効果を感じやすいのが特徴です。
食いしばりによってこわばっていた咬筋(こうきん)や側頭筋がゆるむと、
「顎が軽くなった」「開けやすくなった」「頭の重さが取れた」といった変化を施術直後~翌日に実感される方も多くいます。
また、筋肉の血流が改善することで、顎・こめかみ・首まわりの張り感がやわらぐほか、
頭痛や肩こりの軽減、顔のむくみ改善などの副次的効果も期待できます。
ただし、この段階ではまだ「一時的な緩和」にとどまることが多く、
日常生活やストレスによって再び筋肉が硬くなってしまうケースもあります。
そのため、初期は週1~2回のペースで数回続けることがおすすめです。
継続的な施術で得られる根本的な改善
一方で、自律神経やメンタルへのアプローチは、時間をかけて徐々に変化していくものです。
食いしばりの背景には「緊張しやすい体質」「ストレス反応」「睡眠の質の低下」などが関係しており、
これらを整えるには数週間~数か月単位の継続的な施術が効果的です。
継続することで、交感神経の過剰な働きが抑えられ、
「寝ている間に歯を噛み締めなくなった」「朝の顎の痛みが出にくくなった」
といった根本的な改善につながっていきます。
さらに、心身の緊張が取れていくことで、
「以前より力を抜けるようになった」「感情的にも穏やかになった」と感じる方も多く、
鍼治療は単なる対症療法ではなく、再発を防ぐための体づくりでそれが根本改善になります。
食いしばりの治療法
当院でのおこなう食いしばりの治療では以下の順番で行っています。
1)腹部の鍼とお灸で内臓ケア
内臓の不調を取り除くことで自律神経の興奮を防ぐ効果があります。
2)顎周囲の鍼で咬筋全体を緩める
食いしばりで使う筋肉全体を緩めます。さらに痛みをおこしている筋肉については少し深めに刺激をしてピンポイントで改善します。
3)頭部や顔面部の鍼で炎症を改善
鼻炎や睡眠不足による脳疲労があることで、睡眠中の食いしばりを起こす原因となるので炎症を軽減する鍼をします。
4)首や肩の筋肉の緊張緩和
顎を使うときに首や肩も同時に緊張します。それらの痛みや硬さが食いしばりを引き起こす原因になるので緩めていきます。
食いしばりのセルフケア対処法
食いしばりのセルフケア対処法
食いしばりは、日常生活の中で少し意識を変えるだけでも軽減できる場合があります。
ここでは、自宅でできるセルフケアの具体的な方法を紹介します。
1. 顎まわりのストレッチ・マッサージ
咬筋(こうきん)や側頭筋など、噛む筋肉をやさしくほぐすことで緊張を和らげます。
・人差し指と中指で頬の下(奥歯のあたり)を軽く押しながら円を描くようにマッサージ
・こめかみ(側頭筋)を指の腹でゆっくりと回す
・口を「アー」と言うように開け、顎の動きを確認しながらゆっくり動かす
ポイントは「痛気持ちいい程度」で、強く押さないこと。
お風呂上がりなど、体が温まったタイミングで行うと効果的です。
2. 姿勢を整える
猫背やうつむき姿勢は下顎を前方に引っ張り、食いしばりを誘発します。
・画面の高さを目線と合わせる
・背中を伸ばして、軽く顎を引く
・肩を後ろに開くように深呼吸を行う
1時間に一度は姿勢をリセットする習慣をつけましょう。
3. 温めて血流を促す
顎や首の筋肉が冷えると硬くなり、力が抜けにくくなります。
ホットタオルや入浴で温め、筋肉を柔らかく保ちましょう。
また、寝る前に深呼吸をしてから布団に入ることで、リラックス状態をつくりやすくなります。
4. ストレスを溜めない習慣を
ストレスや感情の抑圧も食いしばりの大きな要因です。
・一日の中で「何もしない時間」を意識的に作る
・軽い運動や深呼吸で気分転換をする
・自分の感情をノートに書き出す
心の緊張をほぐすことは、体の緊張を和らげる近道です。
またストレスに直面したときに食いしばりで解消しないように他の方法を設定しておくことも有効な方法です。
5. 寝る姿勢・環境を整える
仰向けで寝ると顎や頬の筋肉がリラックスしやすくなります。
枕が高すぎたり横向き寝が多いと、顎に偏った力がかかるため注意が必要です。
また、寝る直前のスマホ・カフェイン・アルコールを控えることで、睡眠中の食いしばりを予防できます。
食いしばり×鍼治療のQ&A
当院には毎月多くの食いしばりで悩む患者さんから問い合わせがありますが、そのときによく聞かれる質問について紹介します。
同じ不安をお持ちであれば少しも鍼灸を選ぶことの不安を解消して下さい。
Q1. 鍼は痛いですか?怖くて躊躇しています
鍼治療に使う鍼は、髪の毛ほどの細さ(直径0.12~0.18mm)で、注射針とはまったく異なります。
刺すというよりも「肌の表面にスッと入る」感覚に近く、多くの方が「思ったより痛くなかった」と驚かれます。
また、当院のように筋肉の反応を丁寧に見ながら最小限の刺激で施術するスタイルでは、痛みや恐怖を感じにくいのが特徴です。
もし不安がある場合は、初回に「浅め・少なめ」から始めることも可能です。
Q2. 何回くらいで効果を実感できますか?
個人差はありますが、筋肉のこわばりによる食いしばりであれば、1?3回で変化を感じる方が多いです。
「顎が軽くなった」「朝のだるさが減った」「頭がスッキリした」といった実感が出やすい段階です。
一方で、自律神経やメンタル的な緊張が関係しているタイプは、体質改善を含めて数週間~数か月の継続が理想です。
鍼は「続けるほど体が緊張を覚えにくくなる」性質があるため、週1回ペースで6~12回程度を目安に考えるとよいでしょう。
Q3. マウスピースと併用しても大丈夫?
はい、マウスピースとの併用は問題ありません。
最近のマウスピースは改良されて上下の歯を固定できるタイプもありますので、そのほうがより効果的です。
むしろ、鍼で筋肉の緊張をゆるめることでマウスピースがより快適に使えるようになり、
「以前は違和感があって外してしまっていたけど、今は気にならない」という方も多くいます。
歯の摩耗を防ぐマウスピースと、根本原因である筋緊張を整える鍼治療を組み合わせることで、症状の再発予防にもつながります。
まとめ
食いしばりは、単なる「噛み締めの癖」ではなく、筋肉の緊張・自律神経の乱れ・ストレスなどが複雑に関係する全身のサインです。ただの食いしばりと思わず、あらゆる症状の入口にいると考えて神経に改善することおすすめします。
マウスピースでの保護やセルフケアも大切ですが、根本的な改善には「体の緊張を解くこと」と「自律神経を整えること」が欠かせません。
鍼治療は、
・咬筋・側頭筋などの筋肉のこわばりをゆるめる即効性
・自律神経や感情面への穏やかな持続的効果
を同時に得られる、数少ないアプローチです。
「朝、顎が痛い」「マウスピースが合わない」「ストレスで噛み締めてしまう」――
そんな方こそ、鍼によるやさしい治療で、本来の“力を抜ける体”を取り戻すきっかけを作ってみてください。
鍼は食いしばりの症状を抑えるだけでなく、
「頑張りすぎてしまうあなたの体を休ませる時間」にもなります。
体と心の両面から整えることで、再発しにくい快適な毎日を取り戻していきましょう。
当院「ミントはり灸院」は、根本から改善することに特化した神戸の鍼灸院です《年間10,000人超の実績》。六甲道駅3分”六甲院”/三ノ宮駅6分”三ノ宮院”/明石駅5分”明石院”の3店舗がございます。全室個室でマンツーマンで施術しています、ぜひお越しください。