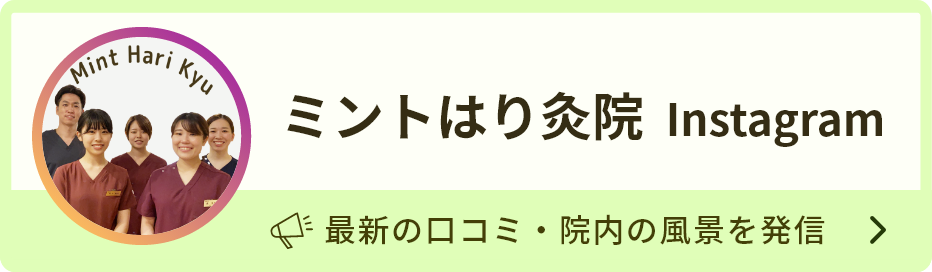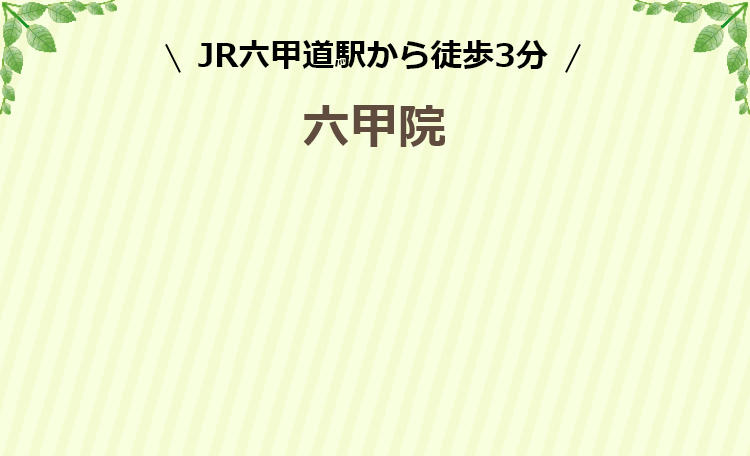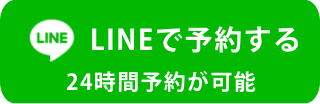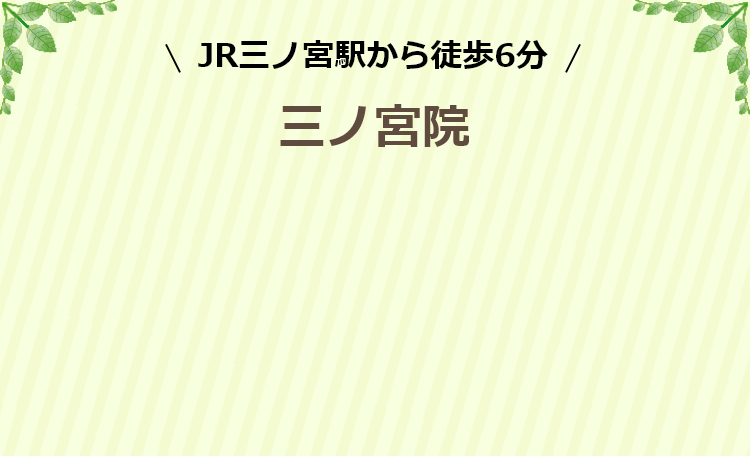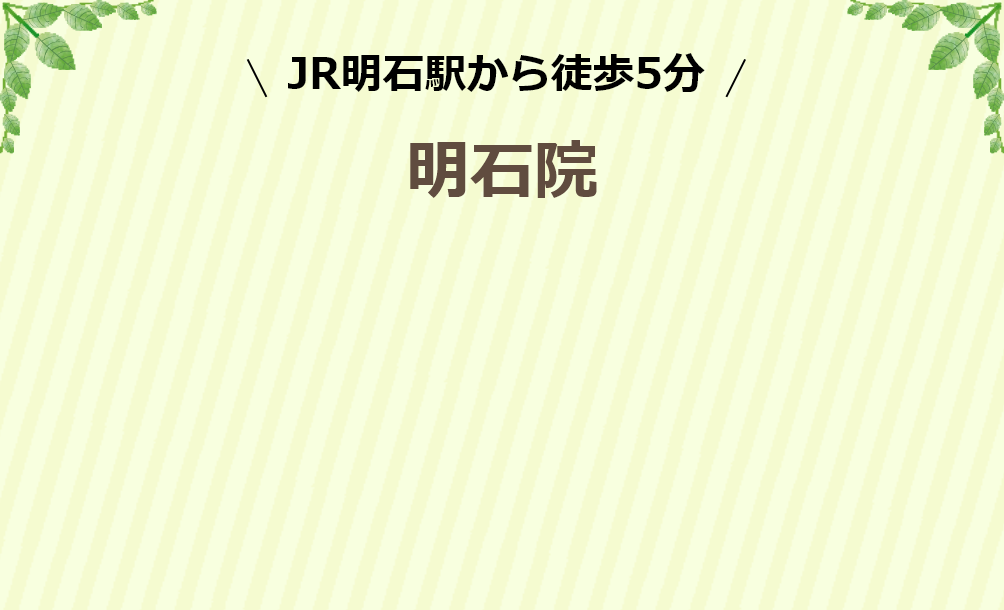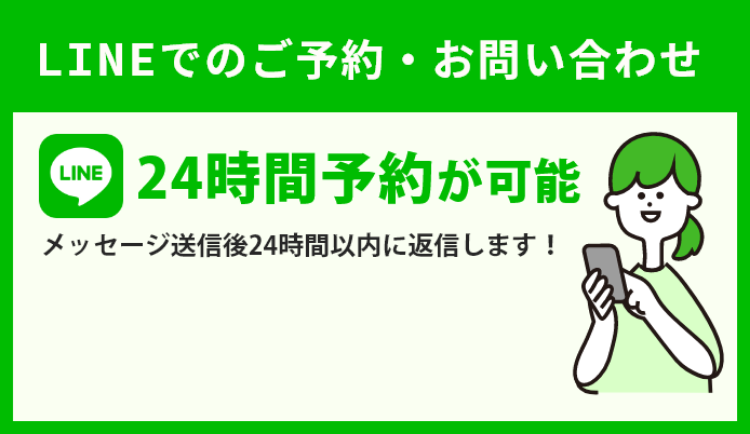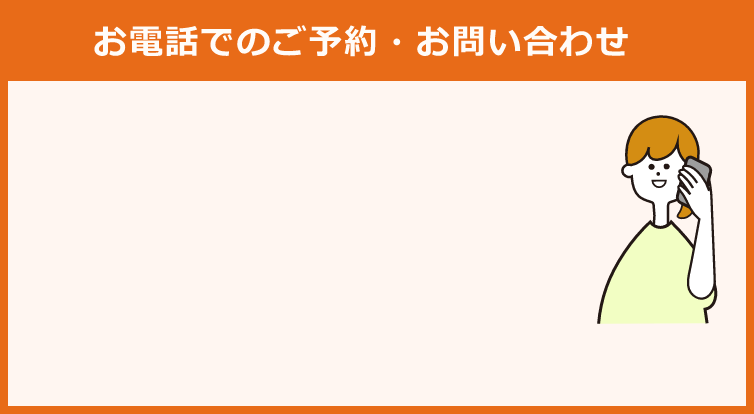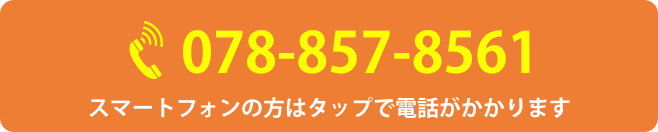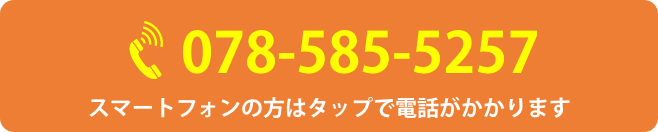投稿日:2025年4月17日
鍼灸ってどのくらいで効果が出るの?回数・頻度の目安を紹介
カテゴリ: Q&A(よくある質問)
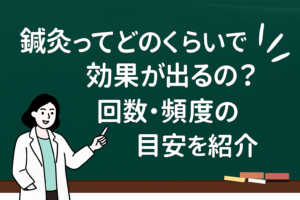
鍼灸は通うものという認識をお持ちの方は多いと思います。
ただ、自分の症状はどれくらい通えば良くなるのか?頻度や期間については不透明ですよね。
頻度や期間がよくわかっていないと、忙しい毎日なのに続けられるか?続けられないなら行く意味がなくなってしまう?と不安に感じてしまうことはないでしょうか?
マッサージのように「最近忙しくて疲れたから行こう」「頑張っている自分へのご褒美に行こう」という付き合い方も悪くないですが、鍼灸院を上手に使うにはちょっともったいないところがあります。
今回は回数と効果について、そしてそこから考える健康的な毎日を維持する付き合い方について解説していきます。
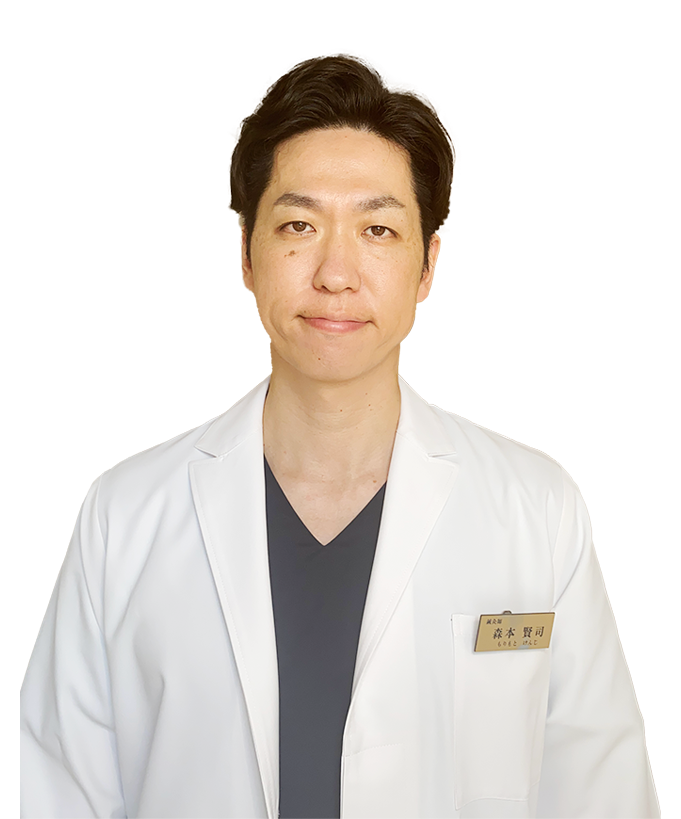
この記事の執筆者
ミントはり灸院 院長
森本 賢司
高度専門鍼灸師
【略歴】
神戸東洋医療学院卒業
神戸東洋医療学院にて河村廣定先生に師事
明治国際医療大学 大学院 修士課程 修了
神戸東洋医療学院 非常勤講師
【資格】
はり師免許証・きゅう師免許証
鍼灸は何回くらいで効果が出る?
まず最初に疑問に思うのは効果を感じる回数についてではないでしょうか?
ある程度期間が必要だと言われたとしても、少し形とも体の変化がないと通うモチベーションが保てなくなります。
自分の症状に対しての鍼灸院や鍼灸師との相性なども考え直したくなりますよね。
急性症状と慢性症状の違い
ぎっくり腰や急な肩の痛みなどの症状については初回から体の変化を出すことができます。程度によっては1回で改善してその時点で終了というのもあるでしょう。
一方で3ヶ月以上悩んでいる症状の場合は3回から5回くらいは治療しないと体の変化を感じることができません。これは症状の改善ではなく、あくまで体の変化です。
症状を起こしている原因は複数の症状を同時に起こしている場合がありますが、その複数症状の軽いものから楽になっていきます。重いものが治したい症状であることが多くなります。
例えば背中の痛みの場合、心臓の不調が考えられます。そういう場合は体全体のむくみも発生している可能性がありますが、背中の痛みであまり気になっていない場合があります。施術を受けると、むくみが先に改善してくということです。
これは心臓の状態は良くなっているから、むくみは改善しているのですが、痛みが強いところは長期間の緊張によって、筋肉が固くなっている可能性がありますので回復に時間を要するというわけです。
そう思うと急性症状ももともとは慢性症状の発展型であることが考えられます。というか多くの症状がそうだったりします。
慢性的な腰の緊張があって、たまたま長時間車を運転して負荷が集中する、車をバックするときに振り向いた瞬間に「グキッ」って筋肉が損傷する。という経緯があると。
ぎっくり腰の治療はその場の痛みを取る治療になりますが、本当に改善するべきは慢性腰痛です。
その場合の治療計画は期間や頻度が変わってきますし、効果を感じる回数も増減する場合があります。
まとめると、効果を感じる回数というのは症状よりも状態で決まるというわけです。
どの症状、悩みを改善したいかで回数が変わってくるということを知っておいて、鍼灸院を利用するときは「〇〇を治したい」と伝えるのも適正な回数を教えてくれると思います。
1回で効く人、複数回が必要な人
このような質問を受けることがありますが、これは治療の相性ではありません。
鍼灸師は身体の状態を判断して、施術する場所を決めますが、それが合っているか、合っていないかは経験などで正答率が変わってきます。
ただ、経験が合ったとしても100か0かという話ではありません。経験による差はせいぜい3割バッターか3割届かないバッターの違いぐらいです。
色んな可能性を一つ一つ排除していくだけなんですね。
経験の長さに関係なく、いずれは正しい場所に施術されるときが来ます。それで1回で終わるところが10回になるとかはなく、せいぜい1回が3回くらいに変わるぐらいと考えてください。
ではこの質問が発生する理由は「状態の見積もりが認識と違う」場合です。
患者さんとしては1回で治るかな?と思っていたら複数回の治療をしないと改善しなかった、逆に5回くらい必要かな?と思っていたら1回で改善した。という経験値があるからこの疑問が生まれるわけです。
そういう場合に1回で効く人がいるのかな?と思ってしまいますよね。
鍼灸はその原理上、体に変化をもたらすことができます。そこに個人差はありません。
違いがあるのは症状と原因の程度の違いだと思ってください。
理想的な通院ペースとは
鍼灸施術は体に変化をもたらしますが、その変化は時間経過とともに少しずつ最初の状態に戻っていきます。
戻り切る前に施術を受けて、前よりもよい身体の状態にしていく、階段を登っていくように状態を高めていくイメージです。
なので通院の間隔というのは「体が戻る前に次の施術」ということになります。
これは薬や筋トレ、勉強などでも同じ原理です。
人間の体の変化は時間経過とともに基に戻っていきます。
一気に治療したら改善するかと言うとそうではないわけです。
薬には適切なタイミング、適切な量を指示されますよね。
鍼灸も同じだと考えてください。
週1~2回がベースになる理由
ただ、多くの鍼灸院の場合は週に1回から2回を治療頻度として提案されることが多いと思います。
これにはいくつかの理由があります。
・時間的や金銭的な負担を重くしすぎない
・やる気を消費しすぎない
・筋トレと同じ原理
あまり施術頻度が多くなると、どうしても負担感が強くなります。
多くの鍼灸院は施術の時間は平均すると1時間程度のところが多いので、準備や移動のことを考えると2時間くらいは必要なりますよね。
1日の活動時間のうちの2時間は非常に大きいわけです。
最初はこそはモチベーション高く通うことはできるかもしれません。ただ人のモチベーションはいつまでも続くわけではありません。徐々に減ってきたときに、通院が重荷になってしまい通うことができなくなってしまうからです。
また効果を出すという意味において、週に1~2というのは効率的な頻度ということもあります。
これは筋トレなどの論文でも書いていますが、週に1回程度でも効果があり、2回がもっとも効果が高いと報告されています。3回を超えてくると効果の上昇が低下しむしろ疲労などが蓄積して効率が下がるという内容です。
鍼灸は筋トレと違うじゃないの?と思うかもしれませんが、原理的には神経への刺激と考えると非常に近いところがありますので、この効果の効率性は私は近しいところにあると考えています。
以上のことから、基本的には週に1回。すこし急いで改善していきたいなら2回というのが基本になってきます。
症状に合わせた個別対応の考え方
一方で回数に関係なく治療を適宜していくこともあります。
これは短期的な効果を狙っている場合です。
翌日に大事な大会がある。その日に不妊治療の移植。明日は同窓会。などなど・・・
鍼灸には即効性を出すこともでき、施術を受けた瞬間からある程度の期間まで体が普段よりも良い状態(血流量が多い)が維持されるのでその効果を使って、大事に日に向けて体をブーストするイメージで施術を入れます。
他にも、メンテナンス、予防的な考えの治療です。
これは月に1回などの間隔でおこなう治療ですが、治療効果というよりも体のチェックや不調が起こりそうなところの予測をしておくことで、不調になるのを未然に防ぐことが目的です。
症状がなく、普段の生活の疲れが徐々にしか溜まっていかない状態にあれば、健康を維持できるのでもっとも効率の良い鍼灸院の付き合い方とも言えます。
毎日受けても大丈夫?
効果があって、短期的な効果も期待したいし、毎日受けてもいいんじゃね?
という疑問がありますよね。
鍼灸治療は毎日受けても大丈夫です。
実は毎日受けている人というのはいます。
それは線維筋痛症やがんによる痛みがある人の場合です。
鍼灸には痛みに対する抑制効果も強いので、治療を受けることで痛みが軽減しその日が楽に過ごせるということで毎日受ける人もいます。(稀なケースですが)
好転反応との関係
毎日受けたら、好転反応が毎回出るんじゃないの?という心配を持つかもしれませんが、好転反応が起きることはありません。
好転反応は2つの理由で発生します。
1つ目は慣れていなくて恐怖心が強い場合です。
これは自律神経の反射や恐怖感による脳の疲労によるものです。
施術回数が多くなればなるほど、どんどん慣れていくので好転反応は置きないわけです。
2つ目は施術前後の変化です。
体が悪い状態から良い状態への変化が大きい場合に、体の間隔が大きく変わることで、いつもとの違う感覚があって、それを不調と感じる場合があります。
治療頻度が多い人ほど、治療前後の変化は小さくなっていくので、こういった好転反応も発生しなくなります。
ただ、1日ですぐに悪化してしまうほどの重症の場合だと毎回の治療のたびに変化が大きいので好転反応が起きやすくなることもあります。
間隔を詰めるメリットとリスク
週に1回よりは2回のほうが、治療効果の効率性がもっとも高くなります。
結果として治療期間が短くなりますので、症状に悩む日も少なくなってきます。大事な人生の時間をより良く使えるというのが最大のメリットではないでしょうか。
さらに体調回復に期限がある場合(例えば旅行やイベントなど)も間に合わせる意味で頻度を高くしておくのをおすすめしています。
リスクというのは最初に書いた、費用やモチベーションの維持などが難しいと思います。
できるだけ早く良くしたい理由を明確にすることで防ぐことができますので、施術担当者と共有しておくことをおすすめします。
即効性が出る場合・遅れて出る場合
治療において効果が早くでるところと遅く出るところがあります。
これは状態によって決まることもありますが、施術する場所によっても違います。
筋肉や皮膚(肌あれはのぞく)については刺激による変化が非常に早く、変化を感じやすい部位です。
一方で内臓などは刺激を与えたからといって、すぐに変化が出るわけではないので、効果が出てくるのにある程度の期間が必要なります。
なぜ時間の違いがあるかと言うと、それは組織回復にかかる時間がそもそも違うからです。
筋肉:24~72時間
腱・靱帯:1~2週間
骨:3~6週間
皮膚:3~7日(表層)
軟骨:数ヶ月~数年
末梢神経:数週間~数ヶ月
血管:数日~2週間
鍼灸治療でそれからの回復力を高めることはできますが、それでもある程度の期間が必要となります。
体質改善にかかる期間
体質改善は内臓が回復して自律神経の働きが正常になっていく状態になった状態です。
内臓の回復は粘膜の回復になりますので、粘膜は程度の違いはあれど数週間から数ヶ月の期間が必要となります。
内臓機能が正常になれば、自律神経などの働きも安定化してきて、体質が改善された状態になっていきます。
美容鍼をやめるとどうなる?
美容鍼を定期的に受けている人は多いと思います。
施術を受け続けることでリフトアップされた状態が維持されると説明を受けているのではないでしょうか?
リフトアップの原理というのは骨格が変わったわけでも、脂肪がなくなったわけではなく、顔の不要なむくみがすっきりした状態です。
なので、やめてしまうとむくみが出てくるので元の状態に戻っていきます。
効果が持続する期間
体内の水は常に循環していますので、施術による効果に即効性があるだけ、もとに戻っていくのも早いのが特徴です。
皮膚への刺激で一時的であっても水分の循環が増えている状態は維持されますので、美容鍼を受けた後こそ自宅でのセルフケアを続けることでむくみを防ぎやすくなります。
美容医療とはちがって、骨や筋肉などの組織を変えるわけではないので、自然な形での美容を目指す方には良い方法ですが、セルフケアは必ず必要になると考えましょう。
定期的に通うべき理由
皮膚への刺激は皮膚の代謝を早めることが言われています。いわゆるターンオーバーですが、これが新しい皮膚が作られることです。新しい皮膚というのは最も新鮮で美しいわけですから、ターンオーバーが短いことは美しさに繋がります。
また美容鍼灸をうけることでのストレス軽減効果もあります。心地よい刺激によってストレスホルモンが出ることを防ぎます。
ストレスホルモン(コルチゾール)が出る状態が続くと
皮脂分泌の増加:コルチゾールは皮脂腺を刺激し、肌がベタついたり、ニキビや吹き出物ができやすくなります。
バリア機能の低下:表皮のバリア機能が弱まり、乾燥肌や敏感肌になりやすくなります。
ターンオーバーの乱れ:肌の新陳代謝が乱れ、くすみやゴワつき、シミができやすくなります。
炎症の増加:アトピーや湿疹などの肌トラブルが生じやすくなります。
このような状態になってしまうのて、定期的な美容鍼を受けることで予防できます。ちなみに通常の鍼灸治療でも同じ効果があります。
まとめ
鍼灸施術の期間や頻度についてさまざまな角度から解説しました。
不調によって悩む日が多くなることが、人生という限られた時間を浪費していると言えます。若い人であれば、それでいろんなチャンスや可能性を失っているかもしれません。
効率よく鍼灸と付き合って、少しでも早く悩みの少ない日、笑顔で遅れる毎日を目指していきましょう。
当院「ミントはり灸院」は、根本から改善することに特化した神戸の鍼灸院です《年間10,000人超の実績》。六甲道駅3分”六甲院”/三ノ宮駅6分”三ノ宮院”/明石駅5分”明石院”の3店舗がございます。全室個室でマンツーマンで施術しています、ぜひお越しください。