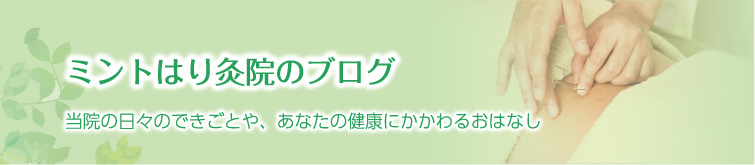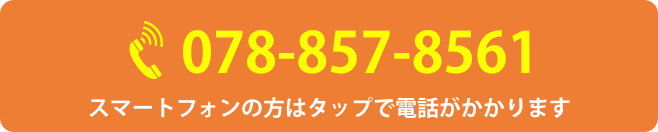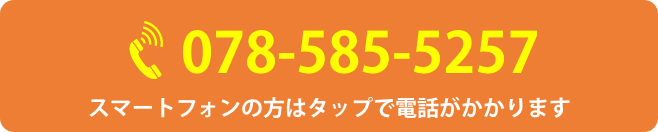症状別の治療
-
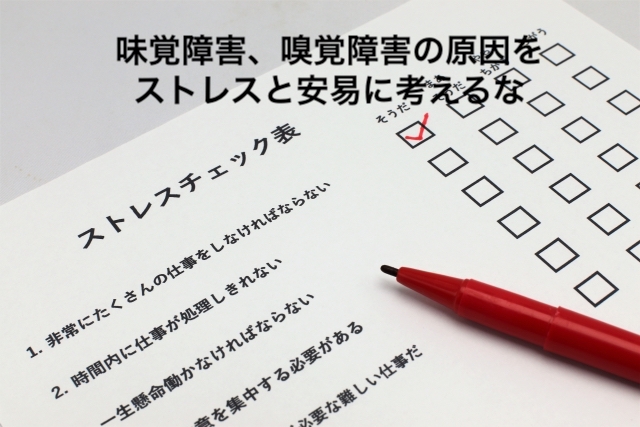
2020年5月23日
味覚障害・嗅覚障害はストレスから!? 味覚障害や嗅覚障害が起きると、亜鉛を処方されることが一般的です。 でも亜鉛を飲んでも治らないケースは少なくありません。 そしてその多くは「原因不明」として、ストレスが原因になっている可能性を指摘されます。 この現代で、全くストレスのない人はなかなかいないと思います。 ストレスと指摘されると「確かにストレスがあるかもしれない」と納得し、本当の原因を見つけられずに…
-

2020年5月22日
味覚障害・嗅覚障害には漢方が効果あり!? 味覚障害は、味が感じられない、違う味に感じてしまう、特定の味だけ分からない、口が乾くといった症状のことを言います。 嗅覚障害も同様に、ニオイが分からない、ずっと焦げ臭い、ニオイに敏感になった、といった症状のことを言います。 そんな味覚障害・嗅覚障害ですが、漢方を飲むことで症状が改善したという声がたくさん挙がっています。 漢方薬局でも、対応している症状として…
-

隠れ鼻炎から嗅覚障害に 当院を受診する患者さんで「隠れ鼻炎」になっている人がたくさんいます。 触診をすると鼻に反応(炎症)がみられるのに、自覚障害がないことが多いのです。 でも話を聞いていくうちに「寝ているときに口呼吸をしていると言われる」「夜寝るときに鼻が詰まることがある」と訴えます。ときには治療していくうちに「鼻が通るようになった。今までずっと鼻が詰まっていたのかも」と言う患者さんもいます。 …
-
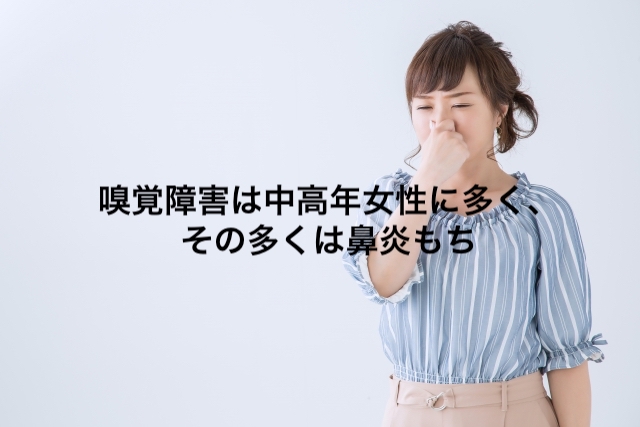
2020年5月19日
嗅覚障害にかかりやすい人とは 嗅覚障害とは、ニオイが分からなくなる、今までとニオイの感じ方が分かる状態を言います。 異臭がする、今までよりもニオイに敏感になった、何を嗅いでも同じニオイに感じるというケースもあります。 味覚とも関係しているので、食べ物の味が感じられにくくなります。そんな嗅覚障害のデータを見ると、年齢が50代の人に多いことが分かっています。 性別が女性が多く、男性と比べると1.5~4…
-
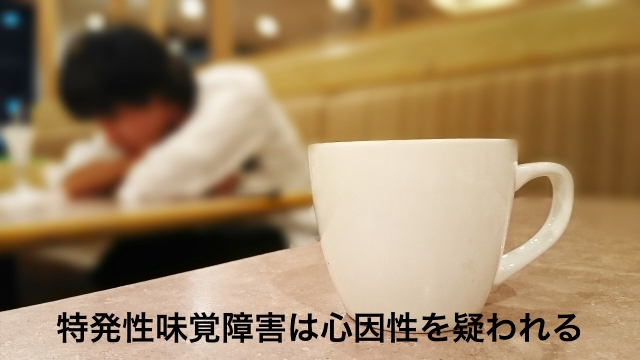
心因性の味覚障害が疑われるケース 味覚障害を発症した人の中で、目立った炎症もない、亜鉛も効かない、胃腸や脳の異常もないといったような状態になる人は、全体の約30%にものぼると言われています。 それほど味覚障害は簡単に「亜鉛不足」と決めつけるような症状ではないのです。自然に治る場合もありますが、長引く場合は心因性を疑われ「うつ病」や「神経症」「心因性味覚障害」と診断されることがあります。 特に口の渇…